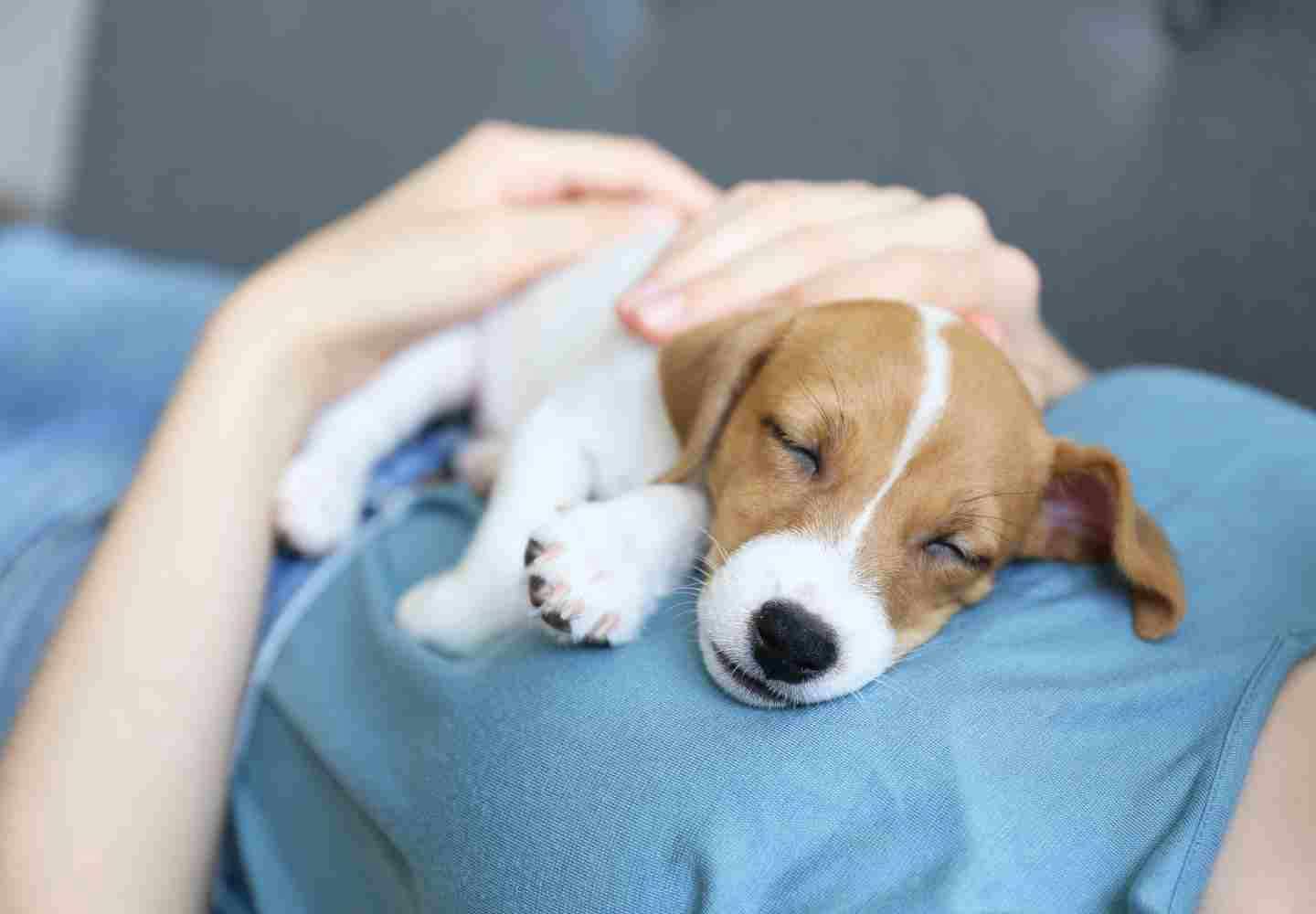2023年12月01日 更新 (2021年12月17日 公開)
chicoどうぶつ診療所所長。体に優しい治療法や家庭でできるケアを広めるため、往診・カウンセリング専門の動物病院を開設。

すやすやと気持ちよさそうに寝ている愛犬。見ているととても癒されますが、大きないびきが聞こえてきたら飼い主さんも心配になってしまうはず。犬も人間と同じようにいびきをかきますが、病気の予兆となっている場合があります。そこで、今回はchicoどうぶつ診療所の所長である林美彩先生に教えていただいた、犬がいびきをかく原因や考えられる病気、対処法などについて解説していきます。
目次
- 犬のいびきの原因は?
- いびきをかきやすい犬はいる?
- 犬のいびきから考えられる病気は?
- 犬にとって危険ないびきの見分け方とは?
- 危険ないびきをする犬を動物病院に連れて行く場合、事前に用意すべきことは?
- 動物病院での犬のいびきの治療法とは?
- 犬がいびきをしている場合、飼い主にできる対処法は?
犬のいびきの原因は?
犬のいびきは、喉がなんらかの影響で狭くなることにより起こります。空気の通り道である上部気道が狭まると、空気が通る際に喉粘膜が振動し、音が発生しいびきをかきます。この原理は人間と同じですが、詳しい原因についても説明していきます。
肥満によるいびき
人間は太っている人ほどいびきをかきやすいですが、それは犬も同じです。喉まわりの脂肪が上部気道を圧迫するため、空気の通り道が狭まってしまうからです。脂肪が多い肥満ぎみの犬ほどいびきが発生しやすくなります。
加齢によるいびき
犬は年齢を重ねると、いびきが発生しやすくなります。その原因は加齢による筋力の衰えです。もともと寝ている間は筋肉が弛緩(しかん)しますが、加齢により首や喉元の筋力が衰えると上部気道をより圧迫してしまいます。
アレルギー・感染症によるいびき
アレルギーや感染症などもいびきの原因となります。理由は喉まわりの炎症です。炎症により喉が腫れて空気の通りが悪くなるといびきにつながります。また、大量に鼻水が発生すると呼吸がしづらくなることも原因のひとつです。タバコの煙や生活環境の変化がきっかけになることもあるので気を付けましょう。
病気により発生するいびき
犬のいびきは心配のいらないものがほとんどですが、なかには病気が潜んでいる場合があります。いびきから考えられるものは、短頭種気道症候群という呼吸関連の病気です。これは、短頭種という鼻がつぶれている犬がなりやすい病気です。他にも口腔内・鼻腔内に腫瘍が発生し、喉や気管などを圧迫するために起こるいびきもあります。
いびきをかきやすい犬はいる?

すべての犬がいびきをかくわけではなく、体つきや年齢、犬種によりいびきをしやすいタイプが存在します。いびきが発生しやすい犬種は、病気につながる危険性も高いため注意が必要です。どのような犬がいびきをかきやすいのか、解説していきます。
肥満ぎみの犬や老犬(シニア犬)
肥満や加齢はいびきの直接的な原因となるため、脂肪が多く太りぎみの犬や、年齢を重ねた老犬(シニア犬)はいびきをかきやすい傾向にあります。特に肥満は生活を正すことで改善される場合もあるため、愛犬のいびきが気になる飼い主さんは食事や運動習慣を振り返ってみましょう。
短頭種の犬
いびきをかきやすい犬種であげられるのは短頭種です。シーズーやパグ、フレンチブルドッグなど鼻がつぶれているタイプが該当します。短頭種はマズルと呼ばれる口まわりから鼻先までの長さが短く、鼻腔のつくりが複雑です。そのため、睡眠中に空気の通り道が狭くなりやすいためいびきが発生します。
また、短頭種の犬は呼吸器系の病気を発症しやすいです。軟口蓋過長症(なんこうがいかちょうしょう)や鼻腔狭窄(びくうきょうさくしょう)などを含む短頭種気道症候群が考えられます。詳しい症状や原因については病気の章でご説明します。
犬のいびきから考えられる病気は?
前述した通り、犬のいびきには病気が隠れている場合があります。ここでは短頭種気道症候群のなかでも軟口蓋過長と鼻孔狭窄について詳しく解説していきましょう。どちらも先天性な要因が多い病気ですので、愛犬への負担を減らす意味でも早めの治療が重要です。
病気について理解していれば早期発見につながりますので、短頭種を飼っている方はぜひ知っておいてくださいね。
軟口蓋過長症
軟口蓋過長症(なんこうがいかちょうしょう)は、口腔内の軟口蓋が通常より長いため、呼吸器系に異常をきたす病気です。
この軟口蓋は、口内の天井部にある硬口蓋からさらに喉元へ近い部分に存在します。食べ物を飲み込むときなどに、鼻のほうへ逆流するのを防ぐ役割を持ちますが、長すぎると喉を狭めいびきにつながりやすくなってしまいます。呼吸障害が起こると、熱をうまく体外に逃せられなくなり、熱中症を発生しやすくなってしまいます。症状が悪化すると呼吸困難を引き起こす場合もあります。
短頭種は生まれつき、軟口蓋の長いタイプが多く、軟口蓋過長症を発生しやすいため注意が必要です。
鼻孔狭窄症
鼻腔狭窄(びくうきょうさくしょう)とは鼻の穴とそれに続く鼻腔と呼ばれる空間が狭まり、呼吸がしづらい状態になる病気です。発症すると、少しの運動でも酸欠を起こしやすくなります。重症化すると、呼吸困難を引き起こす可能性のある危険な病気です。激しい運動後は酸素量の不足を意味するチアノーゼの症状が出ていないか確認するようにしましょう。舌や唇が青紫色に変色していたら危ない状態です。
鼻腔狭窄は先天的なものが多く、短頭種によく見られます。または、アレルギーや感染症で鼻腔内が腫れた場合も起きることもあるので、気を付けましょう。
犬にとって危険ないびきの見分け方とは?

いびきが病気のサインでもあると考えると、愛犬の健康がとても心配ですよね。犬のいびきが病気なのか見極める方法についてご紹介します。
突然いびきをかくようになった
まずは、以前の状態と比べて確認してみましょう。前はいびきをしていなかったが突然いびきをかくようになった、いびきの音が大きくなってきている場合は、動物病院の受診を検討してください。
いびきの最中に呼吸が止まる
いびきの最中に呼吸が止まる、起きているのにいびきに似た音がするなどの症状も注意が必要です。いびき以外にも呼吸が苦しそうだったり、寝る際にあえいでいるなど呼吸器症状の悪化が見られるときも病気が疑われます。
上記はあくまで事例のひとつです。病気は早期発見が大事なので、気になる症状が見られたら、自己判断をせず早めに獣医師に相談してみましょう。
危険ないびきをする犬を動物病院に連れて行く場合、事前に用意すべきことは?
動物病院へ連れていく際には、診断の判断材料となるような情報をまとめて持っていきましょう。いびきの頻度や様子、いつから始まったのかをメモに書いておくとわかりやすいです。いびきが始まったタイミングでの食事や生活環境などの変化も重要な判断材料になるので説明できるように準備しておきましょう。その他、獣医師に聞きたいことがある場合もメモに残しておくと忘れずに聞くことができます。
可能なら、犬がいびきをかいている最中の動画を撮影しましょう。実際の状態が伝わりやすくなるため、獣医師が症状を判断しやすくなります。
動物病院での犬のいびきの治療法とは?

治療法は原因により異なり、薬の投与などの内科療法や手術などの外科療法があります。
内科療法
内科療法は、薬の投与に関してはアレルギーや感染症が原因の場合に行います。原因に合わせて抗アレルギー剤や抗生物質などを投与します。
外科療法
外科療法は、病気により症状が重い場合に手術が必要になります。鼻腔狭窄の場合は鼻腔の拡張手術、軟口蓋過長症では軟口蓋を一部切除する手術が必要になり、いずれも全身麻酔をかけておこないます。重症化すると手術が大掛かりとなり麻酔の負担が大きくなるため、早期対応が鍵となります。
その他、肥満の場合は食事や運動面でのダイエット指導をおこないます。
犬がいびきをしている場合、飼い主にできる対処法は?

病気が原因でない場合、生活習慣や飼育環境が大きく関わっている場合があります。その場合、生活環境を変化させることで、対処・改善できます。原因別に対処法を紹介していきますので、ぜひ取り入れてみてください。
寝る姿勢の改善
寝る際の姿勢を正すと、いびきが治まる場合があります。いびきは上部気道が狭まることで起きるので、仰向けは特にいびきが出やすい姿勢です。うつ伏せで、背中を丸めるような姿勢に直してあげると、呼吸がしやすくいびきが発生しにくくなります。
食事の見直し
肥満が原因の場合は、適正体重に近づけるよう食事を見直しましょう。呼吸器系の病気に限らず、肥満は万病のもとです。さらに、肥満により足や腰などの関節へも負担がかかってしまいます。愛犬の健康管理は飼い主さんの重要な役割なので、定期的な体重測定や体型チェックをしてコントロールしてあげましょう。
まず、毎日の食事やおやつでカロリーを摂りすぎていないか見直してみましょう。ドッグフードの袋には、体重に対しての適正な食事量が記載されているので参考にしてみてください。ただし、基準にするのは目指すべき適正体重です。現在の体重に合わせた食事量を与えるとカロリーオーバーになってしまうので注意しましょう。
運動量の見直し
愛犬が肥満になってしまう原因のひとつは運動不足です。十分な運動量を確保できるよう散歩を欠かさないようにしましょう。小型犬の場合、室内遊びのみという飼い主さんもいますが、散歩は消費カロリーが多いだけでなく、リフレッシュ効果も見込めるためうまく取り入れてみてください。
また、犬種ごとに最適な運動量は異なりますので、しっかり調べる必要があります。わからない場合は獣医師に相談してみてください。動物病院によってはダイエットプログラムを実施しているところもあるため活用してみましょう。
アレルゲンの除去
アレルギーが原因と考えられる場合には、原因の元となるアレルゲンを極力除去する必要があります。犬のアレルギーとして主に考えられるのは、ダニやハウスダストなどです。こまめに部屋の掃除をすると、ある程度は除去できるでしょう。動物病院ではアレルギー検査でアレルゲンを特定できるので、より正確な情報を知りたい場合は検討してみてくださいね。
また、タバコの煙にも気を付けたいところです。タバコの煙は鼻の粘膜を刺激し、鼻水が出やすくなるため、愛犬がいる場所では喫煙しないようにしましょう。
※記事内に掲載されている写真と本文は関係ありません。