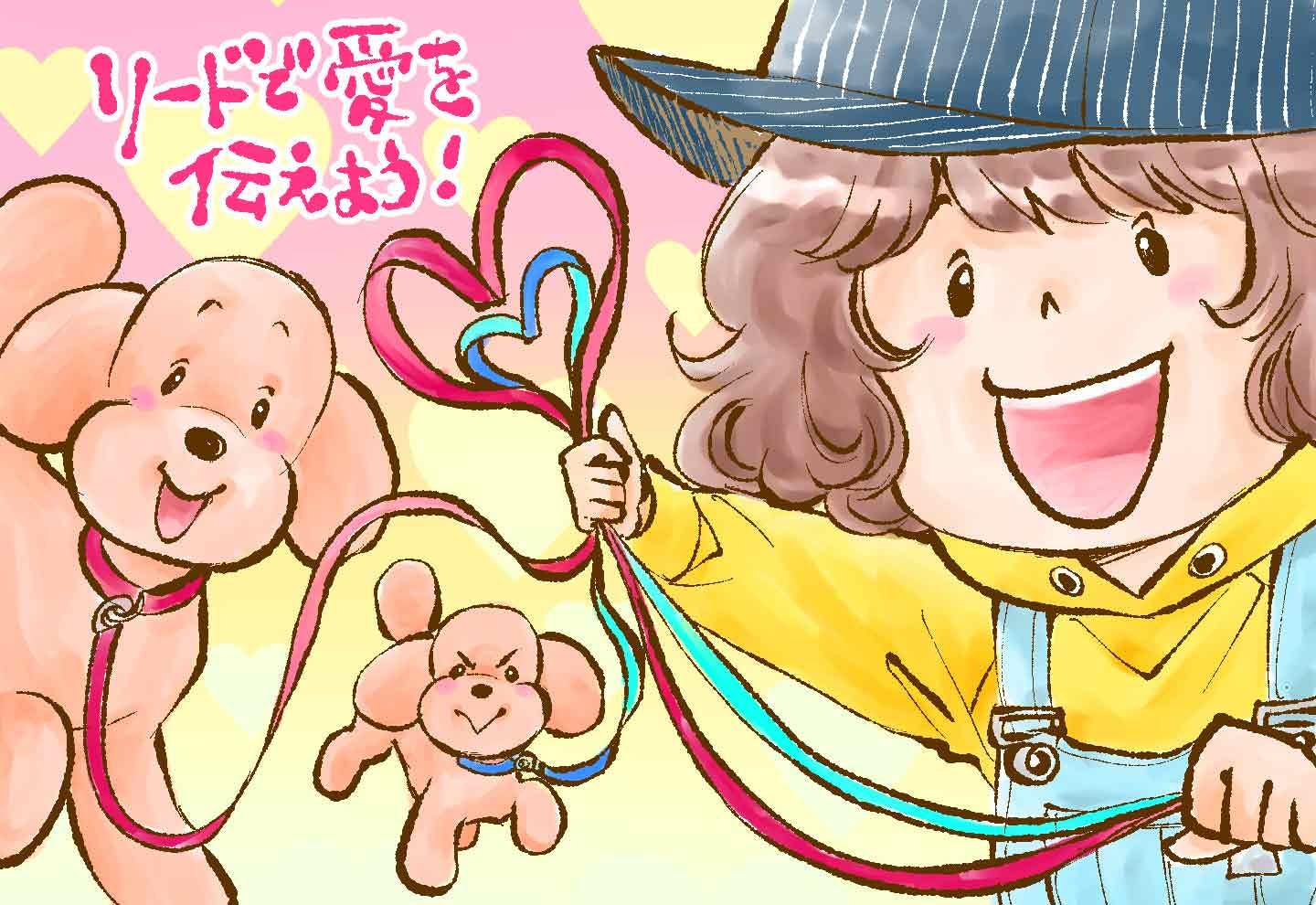2022年09月19日 更新 (2020年09月26日 公開)
博士(獣医学)。専門は獣医動物行動学。evergreen pet clinic ebisu行動診療科担当。日本獣医行動研究会研修医。藤田医科大学客員講師。

家にお迎えした子犬。小さくてかわいらしいだけに、すぐに外に連れて行きたくなりますよね。でもいきなり外に行ってはいけません。散歩デビューはタイミングを選び、しっかりと準備をして臨みましょう。今回はヤマザキ動物看護大学で動物行動学を研究する獣医師の茂木千恵先生に教えていただいた子犬のお散歩デビューのタイミングや準備としてやっておくべきこと、おすすめのコースなどを解説します。
目次
- 子犬の散歩デビューの最適なタイミングはワクチンプログラムが終わってから
- 子犬の散歩デビューの前にやっておくべき練習・しつけは?
- 子犬の初めての散歩はいつ、どんなコースがいい?
- 子犬の散歩中に注意するべきことは?
- 子犬の散歩デビューに必要なアイテムとは?
子犬の散歩デビューの最適なタイミングはワクチンプログラムが終わってから
本格的な散歩デビューはワクチンプログラムが終わってからにしましょう。子犬にはまだ免疫力がありません。感染症などのリスクを考えると、自分の足で外の地面を歩いたり、不特定多数の犬と接触したりするのは避けた方が無難です。
子犬の「社会化」はどうすれば?
世界小動物獣医師会が示す「犬と猫のワクチネーションプログラム」(※1)では、一般的な子犬の場合は6~8週齢で1回目の接種をし、その後16週齢頃までに2〜4週間隔で2・3回の接種をすることを推奨しています。16週というと約4ヶ月。「そんなに長いこと散歩させないの?」と驚く飼い主さんもいるでしょう。
確かにワクチン接種が全部終わるまで待ってしまうと、子犬の時期に社会性を学ぶ「社会化期」を逃してしまいます。社会化期とは人間社会や飼育環境からさまざまな刺激を受け取ることで社会性を養う大切な時期ですが、生後12~16週には終わってしまいます。この時期に外出したり他の動物と触れ合ったりして外的な刺激を十分に受けないと、外からの刺激に対して臆病になってしまう可能性があります。体をワクチンで守ることも大切ですが、心の発達のことも考慮する必要があります。
それらを踏まえると、本格的な散歩デビューはワクチン接種が終わってからが望ましいですが、その前に衛生管理がされている動物病院でのパピープログラムやしつけ・飼い方教室などに参加してみるのがおすすめです。また、ワクチン接種前であっても子犬が他の犬と触れ合ったり、自分の足で直接地面に触れたりしなければ大丈夫なので、抱っこしてのお散歩は問題ありません。一緒に外の風景を楽しみつつ、人や他の犬に会うことにゆっくりと慣れさせましょう。
なお、ワクチンを接種した直後は体調が悪くなりやすいので最後のワクチン接種が終わってから2〜3日は外出を控え様子を見守りましょう。室内で静かに過ごし、シャンプーや激しく興奮させたり走らせたりすることも控えるようにしてください。
子犬の散歩デビューの前にやっておくべき練習・しつけは?

ワクチンプログラムが終われば子犬の体の準備は整ったことになりますが、ワクチンプログラム期間中に散歩デビューの準備や一緒に歩く練習をしておくことも大切です。
首輪やハーネス、リードになれさせる
まずはおやつを与えながら首輪やハーネス、リードを見せ、首輪やハーネス、リードに良いイメージを持たせます。次に実際に首輪やハーネス、リードをつけて部屋の中を歩き、犬が自分の足元についてきたら褒めたり、おやつを与えたりすることで、首輪やハーネス、リードへの抵抗感をなくしていきます。
家の中で一緒に並んで歩く練習
子犬のうちは足元やリードに興奮して噛みついてくるなど、ただ一緒に歩くことさえも難しい場合があるので、歩く練習をしておきましょう。
まず犬と一緒に並んで立ちます。子犬が走り出してしまったらリードを持った手を腰にやったまま立ち止まり、名前を呼んでください。リードが緩まないので子犬は飼い主さんの方を見るでしょう。そのときアイコンタクトができたら褒めてあげて、少し前進します。
家の中で「つけ」で歩く練習
犬が飼い主さんの横にしっかりとついて並んで歩く、「つけ」の状態ができるように練習しておきましょう。
まずリードを右手で握って、左側に犬を座らせます。左手の指先にご褒美のフードを持ち、掌を犬の鼻先に向けます。「座れ」の号令で座ったら褒めて一粒あげます。再びフードを持つ左手を鼻先に近づけ、誘導するように一緒に歩きだします。このとき左手は飼い主さんの膝より前に出さないようにして犬が飼い主さんと歩幅を合わせられるようにします。その間、左手のフードは舐めさせるか少しずつかじらせるようにします。
興奮してきたり、飼い主さんの前に回り込んできたりしてしまったら立ち止まり、最初の位置に戻りましょう。犬が落ち着いたらアイコンタクトを取り、再開します。
短時間の練習を繰り返すのがコツ
散歩のための練習は繰り返し行うことが大切です。この時期の子犬の集中力は5分程度。一度に長く続けるよりも、犬の集中力が続く2〜3分程度で楽しいと思える短時間の練習を何度も行うことを意識してください。
子犬の初めての散歩はいつ、どんなコースがいい?

初めてのお散歩は時間帯やコース選びも重要です。以下のようなポイントを踏まえて検討しましょう。
快適な気候・時間帯を選ぶ
何事も第一印象が大切です。初めてのお散歩デビューで怖い思いやビックリするような経験をしてはお散歩が苦手になってしまいます。できるだけ心地の良い穏やかな日を選びましょう。
天気はできれば晴天が良いですが、夏など日差しが強い場合には薄曇りの日でも構いません。朝や夕方などの涼しくて動きやすい時間帯を選びましょう。
家から近く交通量が少ないコースを選ぶ
飼い主さんにとっては見知った近所でも、犬にとっては未知の世界。まずは玄関や庭、次に家の周りと少しずつ行動範囲を広げましょう。何かあってもすぐに戻ることができ、犬も安心して周囲を観察できます。
車やバイクの接近を怖がることがあるので、自宅の周りの交通量が多い場合は、まずは抱っこして外に出て、ゆっくり落ち着いて歩ける場所にきたら地面に降ろして歩かせた方が良いでしょう。
短い時間でOK
初めは体を動かすことより環境に慣れることが第一なので時間は短く、子犬の集中力が持つ5〜10分程度が目安です。犬が嫌がったら無理強いはせず家に戻り、玄関でリセットしてもう一回出てみる。それを毎日続けるようにして少しずつ慣れさせていきます。
子犬の散歩中に注意するべきことは?

子犬にとって外の世界は初めてのことばかり。たくさんの刺激を受けますが、思わぬトラブルが発生することも。特に最初のうちは初めてのものに子犬がどんな反応をするかよく注意を払いましょう。
誤飲に注意
まず、気をつけるべきなのは誤飲です。好奇心旺盛な子犬は道に落ちているさまざまな物をまず口に入れて味やにおいを探索したがる傾向にあります。特にたばこの吸い殻やプラスチック製の食品梱包材などは命の危険につながりますので、子犬から目を離さないよう注意してください。
もし、子犬が口に入れてしまいそうなものが落ちていたら高い声で呼びかけたりご褒美をあげたりしながら飼い主さんに集中して歩くようにして通り過ぎましょう。口にくわえてしまった場合は、慌てず口元にご褒美(フードやおもちゃ)を持っていき交換しましょう。無理やり口を開けて取り上げようとすることは子犬に恐怖を与えますし、慌てて飲み込んでしまうことにもなりかねません。子犬が散歩中に誤飲してしまった場合は、必ずすぐに最寄りの動物病院で診察を受けましょう。
他には犬の排泄物、落ち葉、昆虫なども子犬が好んで口にするものです。飼い主さんが先に見つけて遠ざけられるよう、散歩中は子犬だけではなく必ず周囲にも気を配るようにしましょう。
怖がっていたら無理に歩かせない
中には遺伝的に怖がりであったり、ちょっとしたことにも大きな反応を示したりする子犬もいます。聞き慣れない音や見慣れない人、小さな段差や慣れない感触の地面を怖がることもあります。
嫌がって歩かなくなってしまったときに無理に歩かせようと引っ張ることはかえって踏ん張らせる結果になってしまい逆効果です。おもちゃやフードを使って呼びよせてその場から移動するようにしましょう。ただし一度怖がったからと毎回避けてしまうと成犬になっても苦手なままです。あまり間を空けずに何度も会わせたり経験させたりすることで克服させましょう。
子犬の散歩デビューに必要なアイテムとは?

散歩で必要となる基本的なアイテムを挙げます。初めての散歩に出かける前に揃えておきましょう。
首輪やハーネス
子犬の場合は体格がしっかりしていないため重い首輪は負担になり、散歩嫌いの一因となることもあります。軽くて丈夫な布製などがおすすめです。
引っ張る犬にはハーネスのような胴や胸を固定するタイプの方が首への負担が少ないと考えられていますが、散歩中に犬が引っ張ることを容認すること自体がおすすめできません。引っ張っている犬は首や胴に強い圧を感じてそこからさらに逃れようとさらに引く力を強めてしまうという悪循環に陥りやすく、飼い主さんも体力を消耗してしまいます。アイテムに頼るよりもしっかりと「つけ」で歩けるように練習しましょう。
リード
リードは、本革などは成長してからにしましょう。においをかいでおやつと間違えてかじる癖がついてしまいかねません。
鑑札(かんさつ)と注射済票
犬の飼い主には狂犬病予防法によって以下のことが義務付けられています(※2)。
- 1. 現在居住している市区町村に飼い犬の登録をすること
- 2. 飼い犬に年1回の狂犬病予防注射を受けさせること
- 3. 犬の艦札と注射済票を飼い犬に装着すること
犬の登録をすると「艦札」、狂犬病予防注射をすると「注射済票」が受け取れます。これは登録された犬であること、予防注射を受けた犬であることを証明するものなので必ずつけておきましょう。
迷子札
動物愛護管理法では、家庭で飼っている動物には飼い主の氏名や連絡先などを記載した首輪や迷子札を装着することを飼い主に求めています。飼い主の身元がわかれば、万が一はぐれてしまっても見つかる可能性が高くなります。
水、おやつ
水分補給のために新鮮な飲み水を持っていきます。おやつは少量のドッグフードなどでも良いので、犬が好きな食べ物を用意しておきましょう。
ウンチやおしっこの処理をするグッズ
散歩中の犬の排泄物の処理は飼い主の義務です。おしっこをしたら水で流す、ペットシーツで吸収するなどの対処が必要です。ウンチは袋に入れて持ち帰ってください。専用のウンチ袋には消臭タイプも多いのでおすすめです。消毒用の70%アルコール溶液、次亜塩素酸水なども携帯しておくと良いでしょう。
雨具
雨の日のレインコートは中・大型犬では必須となる場合が多いでしょう。子犬の頃から雨の日に限らず、繰り返し着用して散歩する練習をしておくことでレインコートへの苦手意識を植え付けずに使えるようになります。
おもちゃ
おもちゃがあると散歩の楽しみが増えます。犬の立ち入りがOKな公園などで遊ぶときに使用しましょう。
(※1)出典:「犬と猫のワクチネーションガイドライン」(2006年,世界小動物獣医師会 ワクチネーションガイドライングループ)
(※2)厚生労働省HP「犬の鑑札、注射済票について」より引用
第3稿:2021年10月18日更新
第2稿:2020年11月20日更新
初稿:2020年9月26日公開
※記事内に掲載されている写真と本文は関係ありません。