2022年11月23日 更新 (2022年10月12日 公開)
作家、獣医師。15歳の時に書いた第44回講談社児童文学新人賞佳作を受賞し、作家デビュー。一方、麻布大学大学院獣医学研究科で博士号を取得、獣医師としても活躍。

「子犬」のことを英語では“パピー”と呼びます。では、いつまでを「子犬」と呼ぶのでしょうか。
フードをジュニア用に切り替える時期? 身体が成熟する時期?
今回は様々な面から見る、「パピー期」の定義をお伝えいたします。
また、パピー期ならではのお悩みも多くあります。子犬を飼い始めたものの、思い描いていた理想とのギャップに焦っていませんか。
「他の子と比べて、覚えるのが遅いかも…」
「こんなに〇〇なのは異常かしら」と不安にならないでください。
トイレの失敗・食糞・噛み癖・夜泣き(夜鳴き)・いたずらなどに困った時は、一度、子犬の目線に立って考えてみましょう。原因が分かれば、対処法もみえてきます。
犬は、人間の赤ちゃんよりも速く成長します。大きくなるのはあっという間です。パピー期ならではの可愛さを楽しみながら、社会化やしつけを行っていきましょう。
目次
- 人間に換算すると何歳? 犬の成長と老化のスピード
- 犬を“パピー”と呼べるのはいつまで?
- 犬の精神的な成熟度から見る“パピー期”
- 犬の身体の成熟度から見る“パピー期”
- 子犬フードはいつまであげるべき?
- いつまで子犬をケージ飼いするべき?
- 子犬のトイレトレーニングはいつまでに終わらせるべき?
- 子犬の甘噛みはいつまで続く?
- 子犬の要求吠えはいつまで続く?
- 子犬のやんちゃ・いたずらはいつまで続く?
- 子犬の食糞はいつまで続く?
- 子犬の夜泣き(夜鳴き)はいつまで続く?
- 子犬の性格は家庭環境や飼い主の対応次第!
人間に換算すると何歳? 犬の成長と老化のスピード
『犬は人間の4倍の速さで歳を取る』、と耳にしたことがある方は多いのではないでしょうか。
では、『最初の1年で一気に成長する』ことはご存知ですか。
日本でよく飼われているトイ・プードルやチワワなどの小型犬は、1〜2歳までの成長が著しく早く、3歳以降から少しゆっくりになるのが特徴です。人間の年齢でいうと、1年で20歳くらいにまで急成長します。そして、犬が2歳になる頃には、人間でいうと28歳くらいになっています。その後は大体1年で3~5歳くらいずつ歳をとっていき、16歳くらいで人間で言うと80歳くらいになります。
一方大型犬は、小型犬に比べると1〜2歳までの成長が遅く、3歳以降から一気に成長スピードが早まるのが特徴です。
あまり日本では見かけませんが、セントバーナードなど40キロを超えるような超大型犬は、2年では22歳くらいまでしか成長しませんが、3歳以降から急速に歳を取ります。9歳で80歳を超えるといわれています。(※1)
|
犬の実年齢 |
人間の相当年齢 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
小型犬 (〜10Kg) |
中型犬 (10〜25Kg) |
大型犬 (25〜40Kg) |
超大型犬 (40Kg〜) |
|
|
6ヶ月 |
15歳 |
13歳 |
10歳 |
8歳 |
|
1歳 |
20歳 |
18歳 |
18歳 |
16歳 |
|
2歳 |
28歳 |
27歳 |
27歳 |
22歳 |
|
3歳 |
31歳 |
32歳 |
33歳 |
32歳 |
|
4歳 |
36歳 |
37歳 |
39歳 |
39歳 |
|
5歳 |
40歳 |
40歳 |
45歳 |
48歳 |
|
6歳 |
44歳 |
45歳 |
51歳 |
58歳 |
|
7歳 |
48歳 |
49歳 |
57歳 |
67歳 |
|
8歳 |
52歳 |
54歳 |
63歳 |
76歳 |
|
9歳 |
55歳 |
59歳 |
69歳 |
85歳 |
|
10歳 |
59歳 |
64歳 |
75歳 |
96歳 |
|
11歳 |
62歳 |
67歳 |
80歳 |
105歳 |
|
12歳 |
66歳 |
71歳 |
85歳 |
115歳 |
|
13歳 |
69歳 |
75歳 |
90歳 |
121歳 |
|
14歳 |
73歳 |
79歳 |
96歳 |
|
|
15歳 |
77歳 |
84歳 |
102歳 |
|
|
16歳 |
82歳 |
89歳 |
110歳 |
|
|
17歳 |
86歳 |
95歳 |
||
|
18歳 |
91歳 |
101歳 |
||
|
19歳 |
97歳 |
110歳 |
||
|
20歳 |
100歳 |
|||
(※1)AAHA Canine Life Stage Guidelines 2019
犬を“パピー”と呼べるのはいつまで?
動物の生涯における段階を「ライフステージ」と呼びます。
犬は、パピー期・ジュニア期・成犬期・シニア期・ハイシニア期の5つの段階に分けられます。
しかし、犬の大きさや犬種によっても寿命や成長スピードはさまざまで、一概にいつまでパピーか、ということは言えず、月齢や年齢での明確な基準はありません。
犬の精神的な成熟度から見る“パピー期”
犬の生後1ヶ月~3ヶ月頃(3週齢~12週齢)を社会化期と呼びます。まだ恐怖心がなく、人や他の犬、他の動物などとの関わり方を学ぶのに適した時期です。この時に、あらゆる刺激に慣れるトレーニングを受けることが推奨されています。
動物病院やしつけ教室で開かれている『パピークラス』でも、大体生後4ヶ月くらいまでの月齢の犬を対象にしていることが多いです。
それ以上の月齢の場合は『ジュニアクラス』に分類されます。その頃は、ちょうど人間で言うと中学生〜高校生くらいの時期にあたります。一度覚えたトイレを失敗する、噛み癖が深刻になる、などパピーの時期とは違った悩みが出てくる頃です。
犬の身体の成熟度から見る“パピー期”
医学的に、身体の成熟度で子犬と成犬を分けることもあります。分かりやすい基準でいうと、避妊・去勢の不妊手術の有無です。生後6ヶ月以降であれば、内臓が発達し、麻酔のリスクが低下するため、不妊手術が可能となります。
メスの場合は、初回発情が来る前に避妊手術を行うと、乳腺腫瘍の予防効果が、しなかった場合と比べて99.5%、2回目の発情前に行った場合は92.0%高いとされています。初回発情は大体7-8ヶ月齢で来ることが多いので、心配な場合はその前に避妊手術を済ませることをおすすめします。ちなみに2.5歳以降で避妊手術をしても、乳腺腫瘍の予防効果はないと言われています。(※2)
しかし、成長スピードは犬種によってもさまざまなので、不妊手術に適した時期も犬種によって違います。犬種によっては、成長が終わるのを待って不妊手術を行った方が関節炎のリスクが低いという報告があります。(※3)
小型犬は、大体生後7ヶ月で骨の成長が止まると言われています。しかし成長があまりに遅く、歯も永久歯に生え変わっていないような場合は、1歳くらいまで手術を待つこともあります。
通常より遅くに愛犬の不妊手術をするケース
- 歯の生え変わりが遅い場合
通常は、生後6ヶ月までに、自然にすべての乳歯が抜け、永久歯に生え変わりますが、超小型犬などの極小サイズの犬は、乳歯の生え変わりに遅れが出ることもあります。特に犬歯(きば)の乳歯が抜けず、乳歯と永久歯が並んで生えて二枚歯になってしまったり、6ヶ月時点で永久歯が生えてきていなかったりすることもあります。乳歯遺残は永久歯の並びに悪影響を与えるため、遅くとも1歳になるまでに残った乳歯を抜くのが望ましいとされています。
遺残した乳歯を抜く処置は、不妊手術で麻酔をかけたときに一緒に行うこともありますが、そもそも永久歯が生えていないと乳歯を抜くべきか判断できません。また、もう少し待っていれば乳歯が自然と抜ける可能性もあります。そのため、歯の生え変わりが遅い子は、不妊手術の時期を遅らせて様子を見ることもあります。
- オス犬の潜在精巣の場合
生後1ヶ月以内に、オス犬のお腹の中から精巣が体外に下降してきます。ごく稀に、1ヶ月以上経っても精巣が降りてこず、精巣が体内に留まることがあります。これを『潜在精巣』といいます。放っておくと、将来的に精巣腫瘍になるリスクが14倍高くなるので、去勢手術が望ましいとされていますが、しばらく待っていると降りることもあるので、場合によっては少し様子を見ます。(※4)
よって私の病院では、小型犬の場合、
- 乳歯が生え変わっているか
- オスの場合は精巣がふたつ体外に降りているか
の2点を見て手術時期を決めることが多いです。
中型犬より大きい犬種の場合は、体の成長が終わるのを待つことが多いです。しかし、オス犬でマウンティングがひどい、マーキングをし始めた、などの理由で生活に支障をきたし、飼い主さんが希望した場合は、生後6ヶ月を過ぎていれば不妊手術を行っています。
(※2)Schneider R, Dorn CR, Taylor DO 1969 Factors influencing canine mammary cancer development and postsurgical survival. Journal of theNational Cancer Institute 43:1249-1261
(※3)The role of sex steroids in controlling pubertal growth.
Perry RJ, et al. Clin Endocrinol (Oxf). 2008. PMID: 17645565 Review.Gonadectomy in immature dogs: effects on skeletal, physical, and behavioral development.Salmeri KR, Bloomberg MS, Scruggs SL, Shille V.J Am Vet Med Assoc.1991 Apr 1;198(7):1193-203.PMID: 2045340
(※4)Canine testicular tumors: epidemiologic features of 410 dogs.Hayes HM Jr, Pendergrass TW.Int J Cancer. 1976 Oct 15;18(4):482-7.doi: 10.1002/ijc.2910180413.PMID: 977190
子犬フードはいつまであげるべき?

ミルクや離乳食、サプリメントなど子犬の時期にのみ与えた方がいいとされているものがあり、いつまであげたらいいのかという疑問を耳にすることがあります。
まず離乳食の最適時期は、おおよそ生後3週頃(20日)から8週頃(56日)までです。ペットショップでの犬の販売は生後56日(8週間)以降と定められているため、一般的に飼い主さんが離乳食をあげる機会は少ないといえます。
また、子犬を引き取る際にミルクやサプリなどを一緒に購入するケースが多く見られますが、離乳食を終えた子犬にとって、ミルクやサプリは必ずしも必要なものではありませんので、頃合いをみてやめても良いでしょう。
「総合栄養食」と書かれたフードをしっかり食べているのであれば、特別な理由がないかぎり何かを足さなくても問題なく生きていけます。
はじめの頃はふやかしたドッグフードを1日3回あげるように言われることが多く、いつまで3回食を続ければよいのか悩まれているオーナーさんも多いと思います。
乳歯がしっかりと生え、ドライフードをふやかさずに食べても吐いたりといった消化器症状がなければ、ふやかさずにあげてもよいでしょう。
ただし、これは子犬に限らず犬全般に言えることですが、犬はあまり噛んでフードを食べないため、「ドライフードに水分を混ぜ、ふやかし、すりつぶし、腸が消化しやすい状態まで細かくする」といった作業をすべて胃が行う必要があります。
子犬は消化管の機能が未発達のため、それらをすべて胃に任せると胃に負担がかかりすぎて、消化器トラブルに発展することがあります。また、一度にたくさんのドライフードを食べると、胃の中で思った以上に膨れ、吐くことがあります。
上記のような症状に注意しつつ、徐々に回数を減らしたり、ふやかさずにドライフードをあげていけばよいでしょう。
フードは、不妊手術後、もしくは1歳を過ぎたくらいで成犬用に切り替えるのがおすすめです。
パピーのうちは、「食べない」ことが生死に直結するので、気をつけてあげて下さい。内臓が未発達のため、血糖値がすぐに下がり、低血糖により命を落とすこともあります。少なくとも生後4ヶ月くらいまでは、長時間の絶食は避け、嘔吐などで食べられない時はすぐに動物病院を受診しましょう。下痢でも体重が減ってしまうので、成犬以上に注意が必要です。
いつまで子犬をケージ飼いするべき?
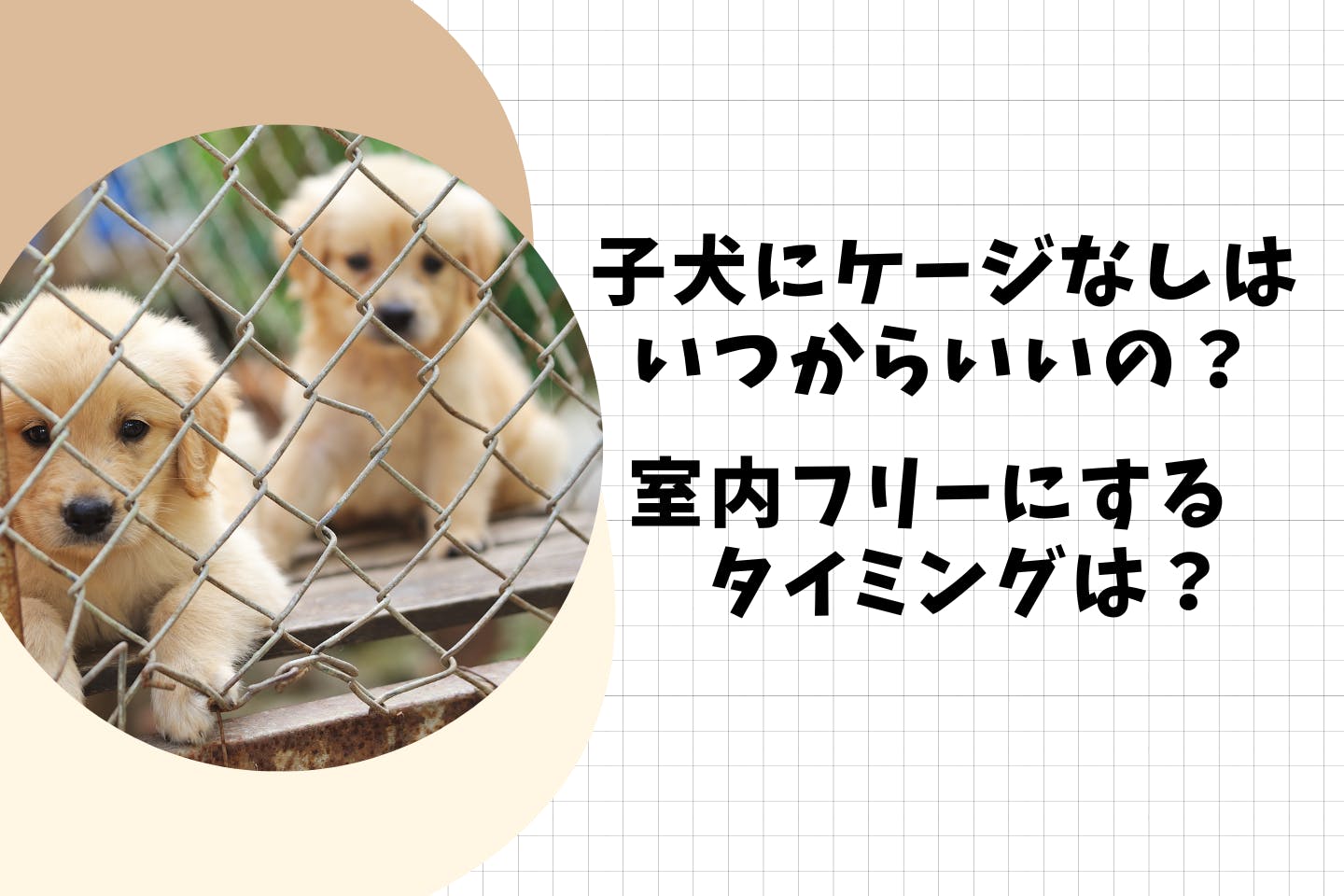
犬を家族として迎える際にケージを一緒に購入される方も多いのではないでしょうか。「子犬をゲージから出す時間」を気にされる方もいますが、落ち着いて部屋を探索できるなら、ずっとケージに閉じ込める必要はありません。
ただ子犬は骨折と異物の誤食がとても多く、どちらも最悪の場合は全身麻酔下での手術が必要になります。部屋の環境を整えないと、お留守番中に室内でフリーにすることは難しいです。ケージから出す前に、まず部屋の環境が愛犬にとって安全か確認しましょう。
とはいえ、無理やりケージに入れてお留守番させていると、ケージを「閉じ込められる嫌な場所」と認識することがあります。「ケージに入れている時はトイレでちゃんとおしっこができるのに、部屋でフリーにしたらトイレを失敗する」という話をよく聞きます。もし犬が「ケージに入ったら閉じ込められる」と思っていたら、わざわざ自分からケージに入ってトイレはしませんよね。また、寝床の近くのトイレが本当は嫌だと思っている可能性も高いです。
ケージには寝床だけを設置し、部屋の中の離れた別の場所にトイレを作り、徐々にフリーにする時間を長くしていくのがおすすめです。
子犬のトイレトレーニングはいつまでに終わらせるべき?

犬を迎えたら、必ず覚えさせなければいけないしつけの一つに「トイレ」があります。トイレトレーニングは飼い始めたその日から始めるようにしましょう。
早くトイレを覚えさせるためには、失敗させないことが大切です。そのためにはおしっこをしそうなときにタイミングよくトイレシートに誘導する必要があります。
子犬は、膀胱内におしっこをためておける時間が短く、高頻度でおしっこをしてしまいます。おしっこを我慢できる時間は月齢×1時間が目安です。
例えば3ヶ月の子犬だったら、3時間しかおしっこを我慢できません。昼間に長時間、子犬をお留守番をさせたならば、必ずその間におしっこを複数回してしまいます。トイレシートにできない時も出てきますよね。そういった「どうしても失敗させてしまう」ような環境の場合は、トイレトレーニングにかかる時間は長引く傾向にあります。
また、夜間は昼間に比べると多少長い時間我慢ができますが、それでもパピーのうちはそう長い時間我慢することはできません。夜に人間が寝るタイミングでおしっこをさせ、朝も5時くらいに起きておしっこをさせると、失敗が減るので、早くトイレトレーニングが進むでしょう。そのうちにだんだん膀胱に溜められる時間が長くなり、朝もおしっこせずに人間の目覚めを待てるようになります。
先ほども述べましたが、生後7〜8ヶ月くらいのオスだと、トイレを失敗し始めることもあります。とにかく子犬ははじめの1年は手がかかりますので、覚悟して余裕のある時に子犬を飼い始めるとよいでしょう。
子犬の甘噛みはいつまで続く?
 子犬はよく甘噛みをします。歯が乳歯から永久歯に生え変わるタイミングで歯が痒くなるからいろんなものを噛みたがる、とよく言われますが、歯が変え変わっても自然には治らない噛み癖も多々あります。
子犬はよく甘噛みをします。歯が乳歯から永久歯に生え変わるタイミングで歯が痒くなるからいろんなものを噛みたがる、とよく言われますが、歯が変え変わっても自然には治らない噛み癖も多々あります。
そもそも、子犬はいろんなものを噛んだり舐めたりすることで、確かめたり、自分を落ち着かせたりします。赤ちゃんが指をしゃぶるのと一緒です。子犬が噛むこと自体は異常行動ではありません。
しかしそれが、人の手や、カーテンなど噛んで欲しくないものの場合は、子犬の行動を修正してあげる必要があります。カーテンは子犬の届かないところで結んで束ねるなど、噛んで困るものは子犬の届く範囲に置かないといった環境改善が重要です。
また、手を噛んでくる場合は、「手を噛んだら遊びは終わり」と覚えさせましょう。手を噛まれたら、さっと手を隠し、数秒間背を向ける。その部屋が安全であれば十数秒間、子犬を置いて部屋の外に出て行くのも有効です。
人の手を噛む行為は、生後6ヶ月で永久歯に生え変わるまでにやめさせましょう。子犬だからと甘噛みを許すと、子犬は「手を噛んでもいいんだ」と学習します。そして、歯が生え変わったあとも手を噛みます。小さい頃許されていたのに、大人になったら急にダメだと言われても、犬は理解できません。大人になってされて困る行為は、小さい頃からしっかりとやめさせて、将来のトラブルを未然に防ぎましょう。
甘噛みでお困りの場合は、ドッグトレーナーやしつけに詳しい獣医師などの専門家に相談しましょう。子犬が小さければ小さいほど、行動修正は簡単です。早めに行動するのが何より大事です。
子犬の要求吠えはいつまで続く?

実は、「要求吠え」は子犬の問題ではありません。そのため、子犬以降の犬に起きがちです。吠える性質があるのか、吠える要因があるのかを探る必要があります。
実際に、子犬が7〜8ヶ月のジュニアに差し掛かり、急に吠えるようになったと驚かれる飼い主さんが多いです。「うちの子はおとなしくて、全然吠えなかったのに…」というおっしゃる方もいます。
しかし、子犬の性格が変わったわけではありません。子犬のうちはあまり吠えないから、その子の吠える性質に気付かなかっただけでしょう。自然界では大きな声を出すと敵に見つかって食べられてしまうリスクが高いため、子犬のうちはあまり吠えないといわれています。しかしやんちゃ盛りのジュニアに入ると、自己主張も始まり、活発な要求が増え、「吠えるようになってしまった」と感じるのです。
犬にとって吠えることも正常行動の一つですが、集合住宅などで吠えられたら困る場合は、吠えにくい犬種を選ぶといいでしょう。例えば、テリアやコリーなど、本来狩りなどの目的のために作られた犬は吠えるのが大事な仕事だったためよく吠えます。
もしくは、吠えては困る刺激(インターホンなど)に徐々に慣らしていく、などのトレーニングを行うと良いでしょう。
子犬のやんちゃ・いたずらはいつまで続く?

想像してみてください。幼稚園や小学校低学年の男の子を、1日なにもない部屋に閉じ込めて出かけたら、帰宅したとき家の中はどうなっていると思いますか? 壁くらい壊されていそうですよね。人間ではこんなことをしたら警察が来てしまうかもしれませんが、子犬にはこういったことをしがちです。
子犬は、エネルギーの塊です。とにかくエネルギーを発散させてあげる必要があります。
子犬時期に起こる問題行動(噛む、吠える、壊す、など人間にとって不都合な行動)は、子犬に適切な刺激を与え、頭を使って疲れさせ、しっかりと遊び、エネルギーを発散させてあげると改善することが多いです。
子犬を飼い始めたので仕事を休みます、というわけにはいかないので、お留守番の時間はどうしてもできてしまうことが多いと思います。ただ、それでも、知育トイを使ってフードをあげて頭を使わせる、帰宅後はしっかりおもちゃで遊んで発散させる、などできることはあります。
「今日はこんな遊びで夜までにくたくたに疲れさせるぞ!」と人間側がゲーム感覚で楽しんでみても良いかもしれません。
子犬の食糞はいつまで続く?

子犬はよく自分の糞を食べます。上述の通り消化管が未発達で、便も未消化の状態で出てくるので、便から食べ物のにおいがするので食べてしまうという説もあります。また、自分が排便をした自覚があまりないので、「なにか暖かくておいしそうなにおいのするものが突然近くに現れた!」という感覚で食べている可能性もあります。
食糞を防ぐには、便をすぐに片付けるしかありません。食事の後に排便することが多いので、食事後は近くにスタンバイし、犬が排便したそうな素振りを見つけたらトイレに誘導、うまくできたらご褒美のフードをあげているあいだにさっと便の処理をするのが理想です。
「何日連続でうんちを食べても大丈夫ですか?」と以前食糞でお困りのオーナーさんから真剣に相談されたことがあります。また、犬の歯がきれいだったので、「歯がきれいですね」と褒めたところ「食糞をするたびに歯磨きをしているんです」と返されたこともあります。どちらも成犬のオーナーさんでした。
ちなみに我が家のシェットランドシープドッグも、以前の家に住んでいるときは食糞をすることもありました。お留守番の時間が長かったせいもあるでしょう。引っ越して、1日4回ドッグランで走り回るようになってからは、排便はドッグランで行い、食糞することもなくなりました。
環境やその子の性格次第では、成犬になっても食糞が続くことがあります。残念ながら、これをやれば必ず食糞は治る、というような解決法はありません。
ただ、散歩や食事の時間を決めると、お腹のリズムも整って決まった時間に排便をするようになることもあります。排便の時間がわかれば、すぐに片付けるなどの対策もとりやすいので、検討してみてもよいでしょう。
子犬の夜泣き(夜鳴き)はいつまで続く?
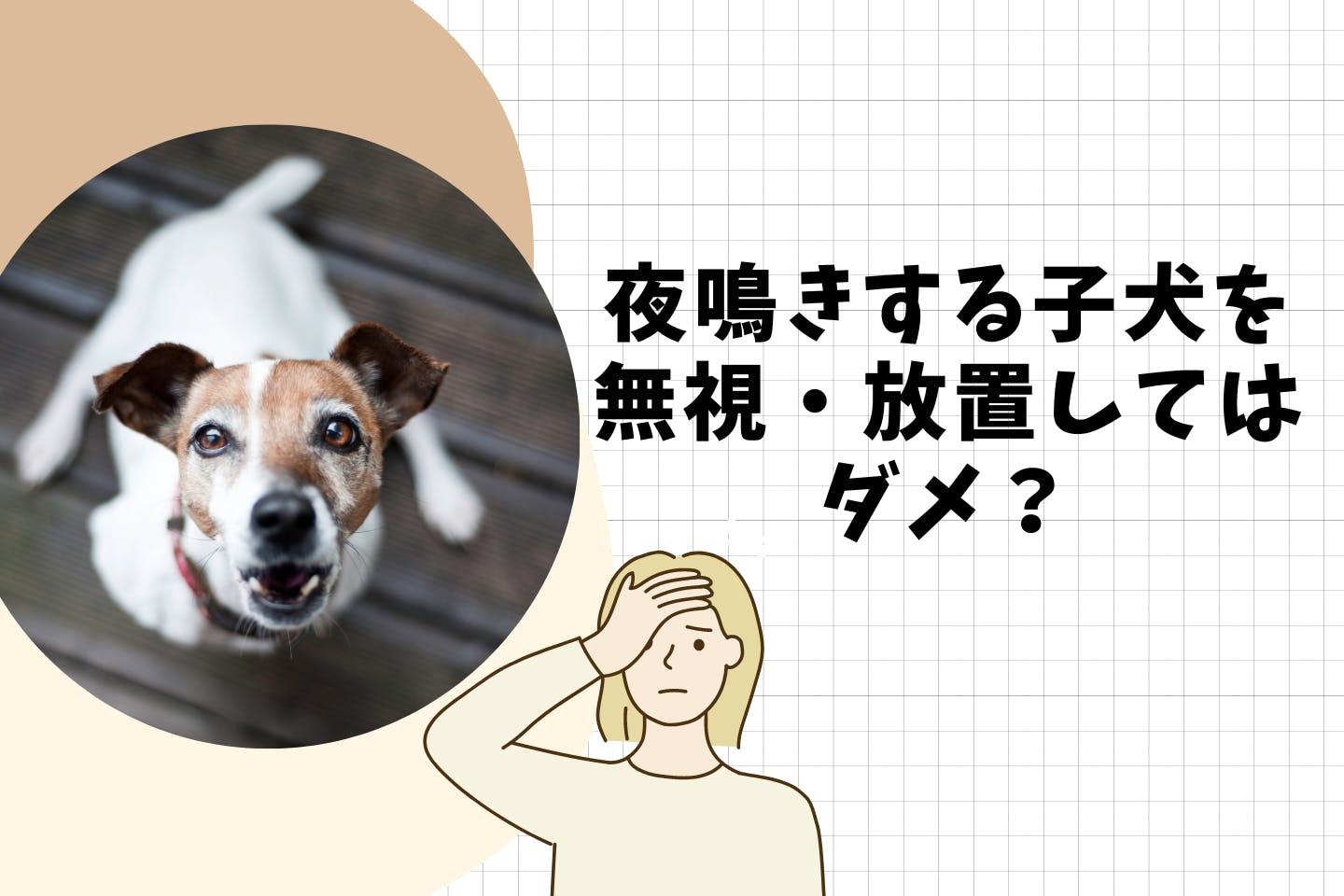
子犬を迎え入れたばかりの頃だと「夜鳴き」に悩まされる飼い主さんのお話もよく聞きます。子犬の夜泣きは原因に応じて、正しい方法で対処すればすぐに収まる場合もあります。そのまま無視や放置をせず、原因を考えてあげましょう。
原因の1つとしては、トイレをしたいから人を呼んでいる可能性が考えられます。上述したように、子犬はあまり長い時間おしっこを我慢できないからです。
ケージ内にベッドとトイレを置いている方は多いと思いますが、本来犬はその状態を好みません。寝ている時すぐにトイレに行きたいからといって、寝室に仕切りもなくトイレを設置している方はあまり見かけませんよね。それと一緒です。犬だって、ベッドの横でおしっこをして寝床をおしっこのにおいで充満させたいとは考えていません。できれば寝床から離れたところで用を足したいと思っています。
子犬に夜中起こされたくなければ、寝る前にトイレをさせ、清潔な寝床で寝かせ、朝は早起きしてまたトイレさせるとよいでしょう。そのうちに膀胱内の成長とともに改善することが多いです。
子犬の性格は家庭環境や飼い主の対応次第!
犬を飼っていると、様々な「問題行動」で頭を悩ませることも多いと思いますが、犬にとってはそれが「正常行動」であることも多々あります。
特に子犬は柔軟で、「待て」や「おすわり」といったコマンドも数回教えただけでできてしまうくらい覚えも成長も早いです。反対に、してほしくないことをさせているうちに、どんどんその行動が強化され、してほしくない行動を覚えてしまうのも早いと言えます。
生まれた瞬間から人に攻撃性を持って噛みつく子犬はいません。環境や周りの対応次第で子犬はどんどん成長しながら変わっていきます。
とくに小型犬は、あっという間に大人になります。困ったことがあったら放っておかず、専門家に相談するのもおすすめです。貴重な子犬のうちに、その後の犬との素敵な暮らしのための土台づくりをしっかり行っていきましょう。














