2023年12月07日 更新 (2022年10月28日 公開)
オールペットクリニック所属。日本獣医皮膚科学会認定医。 アメリカChi University Veterynary Food Therapyコース修了。

うんちは健康のバロメーターと言われています。愛犬の排便回数が減ったり、1日うんちが出なかったりすると、体調が悪いのではないかと不安になってしまいますよね。犬がうんちをしない理由や対処方法を知り、愛犬の健康管理に役立ててください。
目次
- 犬がうんちをしない原因は主に5つ
- 便秘とはどんな症状?便秘を放置すると生じるリスクとは
- 日ごろから意識したい!犬の便秘対策とは?
- 緊急性が疑われる場合は動物病院を受診
- まとめ
犬がうんちをしない原因は主に5つ
犬は比較的排泄を我慢できる動物ですが、愛犬が少しの間でもうんちをしなくなると、「病気なのではないか?」と心配になってしまいます。ここでは、犬がうんちをしないとき、考えられる5つの原因を紹介します。

運動不足
慢性的に運動不足の状態にあると、犬の筋力は衰えてしまいます。すると、排泄の際に踏ん張ったりいきんだりがうまくできず、うんちが出にくくなることがあります。
また、運動不足によって腸の動きが悪くなることも、便秘や排泄困難につながる原因となります。毎日散歩をしていても、運動量は足りているかなど常に気を配ってあげましょう。
栄養の偏りと水分不足
人間にとっては便秘解消に役立つ食物繊維ですが、犬は植物由来の繊維(不溶性繊維)の消化が得意ではないため、与えすぎには注意しなくてはなりません。特に、食物繊維を取り過ぎると、硬くなったうんちが腸を通過できず、結果的に便秘となってしまうことがあります。水分摂取が足りない場合も、便秘を引き起こします。
また、ダイエットフードはカロリーを抑えるために食物繊維が多く含まれているものがあります。愛犬の健康のため与えている場合でも、体重だけでなく、うんちの状態にも注意するようにしてください。
ストレスによる自律神経の乱れ
自律神経は、呼吸や消化、排泄など生きるために必要な機能を自動的に調整しています。自律神経には、交感神経と副交感神経があり、胃腸の働きは副交感神経が活発になることで高まり、消化や排便が促されます。
犬にとって過度なストレスは自律神経の乱れを招きます。例えば、引っ越しや一緒に暮らす家族の増減など、愛犬を取り巻く環境が変化すると、自律神経が乱れ、消化や排便に影響が出て便秘につながるケースもあります。
病気
うんちをしない原因として、病気も考えられます。
例を挙げると、「肛門嚢炎」「肛門周囲腺炎」「会陰ヘルニア」「関節炎」「腫瘍(ガン)」「椎間板ヘルニア」などがあります。これらの病気にかかると、痛みが原因で踏ん張れずうんちが出ない、便が腸の途中で停滞してうんちが出ないなどが考えられます。
また、オスで去勢していない場合は、「前立腺肥大」や「前立腺炎」が原因でうんちが出ない可能性もあります。
トイレの環境が悪い
トイレが汚れていたり、飼い犬の頭数の割にトイレが少なかったりなど、トイレ環境の悪さも排便に影響を与えることがあります。トイレ環境が悪いために、犬がうんちを我慢してしまい、便秘につながるケースもあります。
綺麗好きで、一度排泄したところではしたがらない犬もいますので、愛犬がいつでも気持ちよく排便できるように、落ち着いて排便できる場所にトイレを設置し、清潔さを保つようにしてください。
愛犬がトイレを我慢するケースについて、詳しく知りたい方はこちらの記事もおすすめ!
便秘とはどんな症状?便秘を放置すると生じるリスクとは
犬の場合、うんちが出ない状況がどれくらい続くと「便秘」と言うのでしょうか。便秘に気づかず放置してしまった場合のリスクも紹介します。

便秘の症状とは?
犬の排便回数は、個体差によって、また年齢によっても違いがありますが、健康な犬で1日に1~4回ほどといわれています。成犬より子犬のほうが回数が多く、1日に5回以上の排便がある子犬もいますが、成犬になるにしたがって、回数は徐々に減っていきます。
特に注意が必要なのはシニア犬(老犬)です。消化機能などの衰えにより、便が出にくくなり便秘になりやすいと理解しておきましょう。
愛犬が便秘かどうかを知るためには、日ごろから排便のペースやうんちの状態をよく知っておくことが大切です。うんちがある程度は出ている状態でも、以下の症状がある場合は便秘が疑われます。
- うんちが固くコロコロしている
- 排便時にいつもよりいきんだり鳴いたりしている
- 排便しようとすると吐いてしまう
- おなかが張っている
- 食欲が低下している
便秘の症状が続き、通常の排便ペースより明らかに回数が減っている、あるいは2日以上うんちが出ていない状況にあるときは、動物病院で診てもらいましょう。
便秘が招く恐ろしい病気
便秘は、ときに「巨大結腸症」という恐ろしい病気を引き起こすこともあります。猫に多い病気といわれていますが、犬でも注意が必要です。
便秘が続くと、腸の中で便の水分が吸収されて硬くなり、出にくくなります。「巨大結腸症」になると、結腸にたまった便によって腸が膨張し、腸が動かなくなってしまいます。症状が軽く、下剤などで対処できるケースもありますが、症状が重い場合は開腹手術が必要になるケースもあるため、便秘を放置せず早めの対処を心掛けてください。
日ごろから意識したい!犬の便秘対策とは?
犬の健康を守り、便秘させないためには、どのような点に配慮すればいいのでしょうか。ここでは、日常生活で特に注意したい2点の対策を紹介します。

運動不足解消
思いっきり運動させることで、腸の動きが活発になり、便秘予防にもつながります。排泄の際に必要な筋肉を衰えさせないためにも、愛犬が生活の中で体を十分に動かせる工夫をしてあげることが大切です。
小型犬であっても、テリアなどの狩猟犬などは運動量の多い犬種です。犬の大きさにかかわらず、純血種であれば犬のルーツを学ぶ、雑種であれば専門家に相談するなどし、愛犬に必要な運動量を把握しておきましょう。
また、年齢とともに運動量が減ってくるシニア犬や、「毎日散歩しているから大丈夫」と思っている飼い主さんも、運動不足に陥っている可能性がないか、もう一度見直しましょう。
毎日散歩に行っていても便秘になる場合はドッグランで思いっきり走らせたり、散歩コースを坂道の多い道に変更する、歩く速度を速めるなども効果的です。
雨の日やシニア犬で散歩が難しい場合には、おもちゃをつかうなどして、家のなかで適度に体を動かせるような遊びを工夫してみると良いでしょう。
適切な食事と水分を与える
うんちが出にくかったり、便秘になりやすかったりする場合は、愛犬の食生活を見直してみましょう。
〈フードやおやつが合っているか見直す〉
便秘の原因が食べ物にある場合は、主にカルシウムの過剰摂取、食物繊維の過不足が考えられます。
骨系おやつなどのあげすぎは、カルシウムの過剰摂取に繋がり、便秘を引き起こす場合があります。
食物繊維は不足しても摂りすぎていても便秘の原因になる場合があり、特に玄米やキノコ類、豆類や芋などに含まれる不溶性食物繊維は、腸の動きが悪いときに与えると便秘を悪化させることもあるため注意が必要です。
腸を整える目的で、乳酸菌やオリゴ糖が含まれたサプリメント、グリーントライプ(酵素や乳酸菌が豊富に含まれるとされる草食動物の胃やその内容物)、無糖のプレーンヨーグルトなどを毎日の食事に取り入れる方法もあります。
ただし、初めて与える際は少しずつ試してアレルギー反応が起きないか、確認してからにしましょう。
特に、ヨーグルトを与える際は注意が必要です。犬は、牛乳やヨーグルトなどに含まれる乳糖(ラクトース)を分解する酵素が少ないため、これらを摂取すると体調不良を引き起こす場合があります。
ヨーグルトは発酵過程で乳糖がある程度分解されるため、牛乳ほど多く含みませんが、与える際は少量ずつ様子を見ながら与えてください。もし、「おならが増えた」「下痢」「消化不良」「嘔吐」などが生じたら、必ず獣医師に相談しましょう。
なお、犬にとっては脂肪の取り過ぎも体に悪影響を与えます。胃の不調や急性膵炎の原因となる可能性もあるため、フードを見直すときは、脂肪含有量にも注意するようにしてください。
〈水分量を増やす〉
1日の水分摂取量が少ないことも便秘の原因となります。必要な目安量は、体重1kgあたり50~60mlといわれています。食事の際には、水を入れた容器も必ず横に用意して、水分を摂取しやすい環境を整えてください。また、水分量が足りないと感じたらドライフードをふやかす、ウエットフードを取り入れるなどの対策もおすすめです。
犬の便秘に関してさらに詳しく知りたい方はこちらの記事もおすすめ!
緊急性が疑われる場合は動物病院を受診
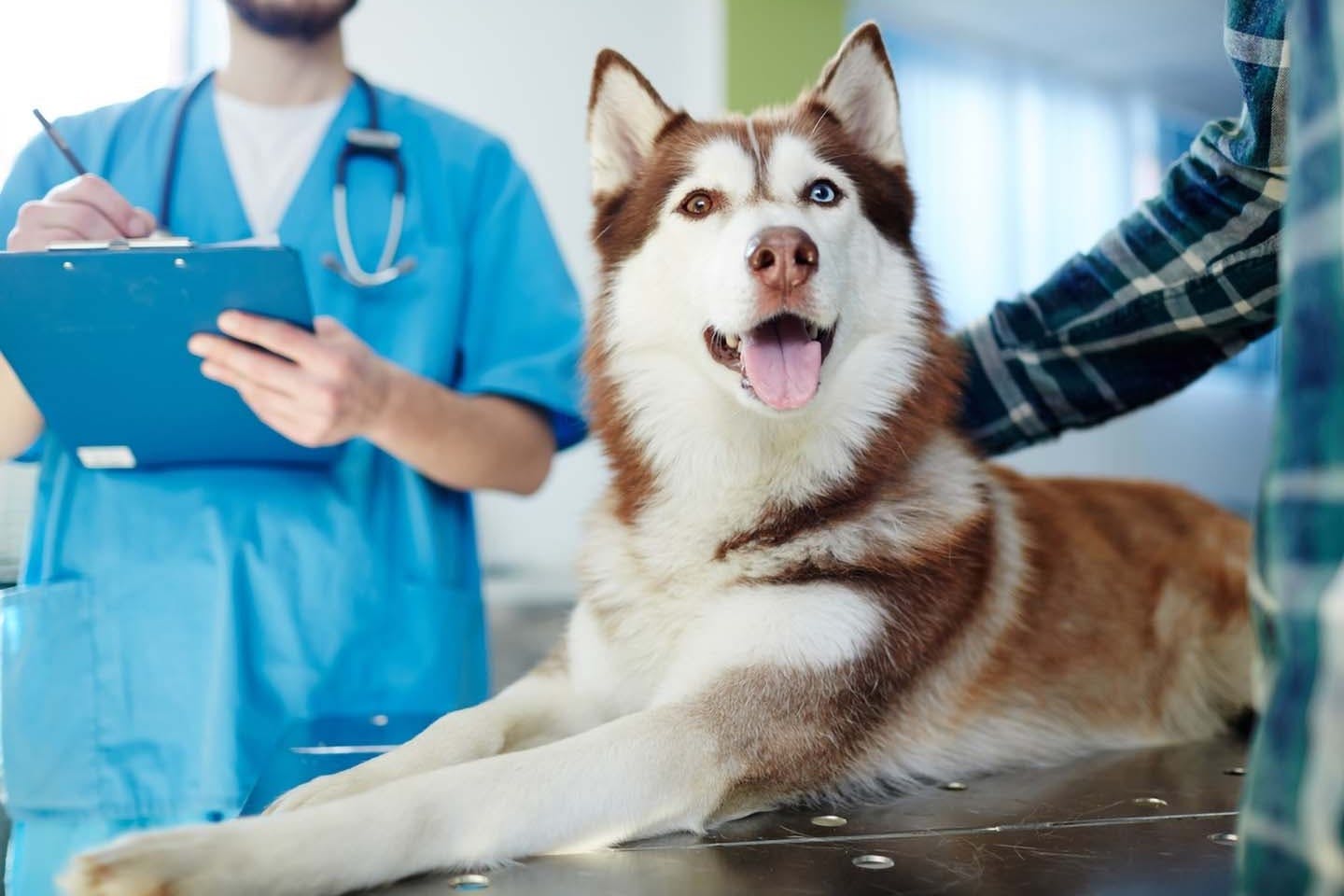
便秘になって1日か2日しか経過していなくても、ぐったりしたり嘔吐したりするなど、他の症状があるときはすぐに病院を受診してください。一つ一つの症状は軽度でも、複数の症状がある場合には、自己判断せずにかかりつけ医に相談することをおすすめします。
受診する際は、日ごろの排便回数やいつから便秘なのかなど細かい点も正確に話せるようにしておくと診断の助けになります。便の写真を携帯で撮影しておき、診察時に見せるのもおススメです。
普段から愛犬の体調や様子をよく観察してメモなどに残しておくと、いざというときに慌てずに済みます。
まとめ

犬がうんちをしない原因として、「運動不足」や「栄養の偏りと水分不足」「自律神経の乱れ」「病気」「トイレ環境の悪さ」などが考えられます。排便回数は犬によって異なりますが、一般的には1日に2〜5回ほどです。子犬のときは回数が多く、年齢が上がるにしたがって減っていきます。
丸2日以上うんちが出ないときはかかりつけ医に相談し、便秘以外にも元気がない、嘔吐するなどの症状があるときは迷わず病院を受診することが重要です。
日頃から運動する習慣をつけ、食生活や摂取する水分量にも注意するなど、愛犬が便秘にならない生活が送れるように環境を整えましょう。










