2023年12月01日 更新 (2021年12月23日 公開)
Animal Life Partner代表。ペット栄養管理士など様々な資格を生かし、診療や往診のほかに、セミナー講師やカウンセリング、製品開発など幅広く活動。

犬の歯は人間の歯とは仕組みが大きく違います。大切な愛犬の歯を守るためにも、正しい知識やケア方法を知っておくことが大切です。今回は、基本的な犬の歯に関する知識から、歯周病の症状や治療法、予防するためのポイントまで、Animal Life Partner代表獣医師の丸田香緒里先生にお聞きした内容を解説していきます。この記事を参考に、愛犬の大事な歯を守ってあげてくださいね。
目次
- 犬の歯の種類と本数は?
- 犬の歯が生え変わるのはいつ?
- 犬がなりやすい歯の病気とは?
- 犬がなりやすい歯周病はどんな病気?
- 犬が歯周病になりやすい理由は?
- 犬がなりやすい歯周病の症状は?
- 犬の歯周病を放置するとどんなリスクがある?
- 犬が歯周病になったときの治療法は?
- 犬の歯周病を予防する方法は?
- 犬の歯磨きはいつから始めたらいいの?
- 犬におすすめの歯ブラシは?
- 犬の歯磨きの頻度と上手に磨くポイントは?
- 犬に人間の歯磨き粉は使用していいの?
- 犬が歯磨きを嫌がるときの対処法は?
- 犬の歯磨きの代わりになるものは?
犬の歯の種類と本数は?
まずは、犬の歯について基本的な知識を押さえましょう。犬の歯は切歯・犬歯・前臼歯・後臼歯で構成されていて、それぞれに役割があります。
切歯
いわゆる前歯のこと。食べ物を切り裂く働きのほか、毛づくろいをしたり、物をかじったりするときに使います。
犬歯
物をしっかりくわえたいときや食べ物を引き裂くときに使われます。肉食動物は特によく発達していて、獲物に噛みつき、致命傷を負わせるための歯です。
前臼歯
いわゆる奥歯のこと。ほとんどの歯が嚙み合わさることがないため、人間の歯のようにすりつぶす役割はありません。ただし、前臼歯にある裂肉歯ははさみのように鋭く尖った形状をしていて、食べ物を小さく切り裂くことができます。
後臼歯
前臼歯より奥に生えている歯。食べ物を細かくしたり、すりつぶしたりする役割があります。草食動物より発達していませんが、物を食べるには欠かせない歯です。
成犬の歯は全部で42本あり、上には口元から奥に向かって切歯6本・犬歯1本・前臼歯4本・後臼歯2本が左右に生えています。下の歯は上の歯に比べ、後臼歯が左右1本ずつ多い状態です。
犬の歯が生え変わるのはいつ?

子犬の乳歯が、永久歯に生え変わり始めるのは生後4か月頃からです。一般的には6か月から1歳を迎える頃までにすべての歯が生え変わると考えられています。
抜けた乳歯は食事と一緒に飲み込まれてしまうこともあり、飼い主が気づかないケースもあるといいます。ただ、飲み込んでしまってもあとから便と一緒に排出されるので、心配する必要はありません。
犬がなりやすい歯の病気とは?
そもそも、犬と人間の口内環境は大きく違います。もちろん、個体差はありますが、多くの犬はあまり咀嚼をせず、食べ物を丸呑みします。また、犬は人間と違って唾液の中に消化液を含みません。そのため、口は食べ物を小さくして胃に送り込むための役割を担っているのです。
このように、人間とは違った口内環境を持つ犬には、かかりやすい歯の病気がいくつかあります。
歯周病
歯垢に含まれる菌によって、歯肉や歯槽骨が融解されることで起こる病気です。
破折(はせつ)
硬いものや、かじってはいけないものをかじって歯が折れたり、欠けたりしてしまった状態。犬はもともと噛む力が強く、また、本来の食べ物ではない物も噛んでしまうため、歯が折れてしまうことが多くあります。また、欠損の際に歯の中心の歯髄から細菌感染を起こし、炎症を起こしてしまう場合があります。
乳歯遺残
永久歯が生える際に抜けるはずの乳歯がそのまま残ってしまった状態です。乳歯遺残自体は病気ではないものの、歯列の乱れや食べ物のカスが詰まりやすくなるなどほかの問題を引き起こす可能性があります。
犬がなりやすい歯周病はどんな病気?

歯周病は歯肉炎・歯周炎の総称です。いずれも歯垢に含まれる細菌によって引き起こされます。
最初の段階で起きる歯肉炎では、歯肉に出血や腫れなどの炎症が見られます。早期に治療すれば完治できますが、放置すると歯周炎に進行します。歯肉炎は歯周ポケットから歯槽骨まで炎症が進んだ状態で、二次疾患を招く恐れがあります。
犬が歯周病になりやすい理由は?
犬が歯周病なりやすい理由の一つは歯磨きの回数が少ないことです。歯周病菌は食べ物のカスをエサにして増殖するため、歯についている歯垢を適切に除去することで防げます。合わせて歯と歯茎の間の歯周ポケットを磨くのも大切です。
また、加齢によって唾液の分泌が減ることも原因のひとつに考えられます。犬は人間のようにうがいができません。そのため、飲んだ水で食べ物のカスを飲み込んだり、口の中をリフレッシュさせたりしています。その水の役割を担うのが唾液です。しかし、高齢になると唾液の量が減るため、口腔内の細菌が増殖しやすい環境になります。
犬がなりやすい歯周病の症状は?

愛犬の口内トラブルを発見するためにも、歯周病の症状を理解しましょう。
歯茎が腫れる
歯肉炎の状態では、歯茎に腫れが見られます。歯周病菌によって歯肉が炎症を起こすためです。
歯茎から出血する
歯肉炎の状態で物を食べたり、こすれたりすると、歯茎から出血が見られることがあります。
歯がグラグラする
歯肉炎が進行すると、歯を支えている靭帯や歯槽骨を歯周病菌が融解してしまうため、歯がグラグラします。
歯が抜ける
歯がグラグラした状態から抜けてしまう場合もあります。グラつく歯を固定することは難しいため、自然に抜けるのを待つか、手術で抜くかを選択しなければいけません。
目の下から膿が出る
歯周病が進行すると、歯の根元に膿の袋ができる根尖膿瘍(こんせんのうよう)が起きます。その袋が破裂すると、膿が外に出てくる場合があります。特に歯石がたまりやすい上顎の第四前臼歯で起こりやすく、目の下から膿が出るといった症状も見られます。
犬の歯周病を放置するとどんなリスクがある?
歯周病を放置すると、歯周病菌によって以下のような症状が出る場合が考えられます。
口臭
食べ物のカスから歯垢が形成されるので、歯周病の進行とともに口臭がきつくなる場合があります。
痛みによる食欲減退
歯周病により痛みや違和感が生じ、食欲不振の症状が見られます。
歯周組織の破壊
歯周炎まで症状が進行すると、歯を支える歯周組織が破壊されます。
歯根腫瘍
別名、根尖膿瘍(こんせんのうよう)と呼ばれ、歯の根元に膿ができる症状です。破裂すると、膿が外に出てくる場合があります。
顎の骨折
歯周病菌により顎の骨の融解が進むと、もろくなった影響で骨が折れてしまう場合があります。
鼻炎/呼吸器感染症
犬歯の歯根は鼻腔近くにまで達しているため、歯周病が進むと炎症により鼻炎のような呼吸器感染症を発症するケースが多いです。
腎臓病/心臓病
炎症部位から血管に細菌が入り、心臓や腎臓に悪影響を及ぼす可能性も考えられます。
犬が歯周病になったときの治療法は?
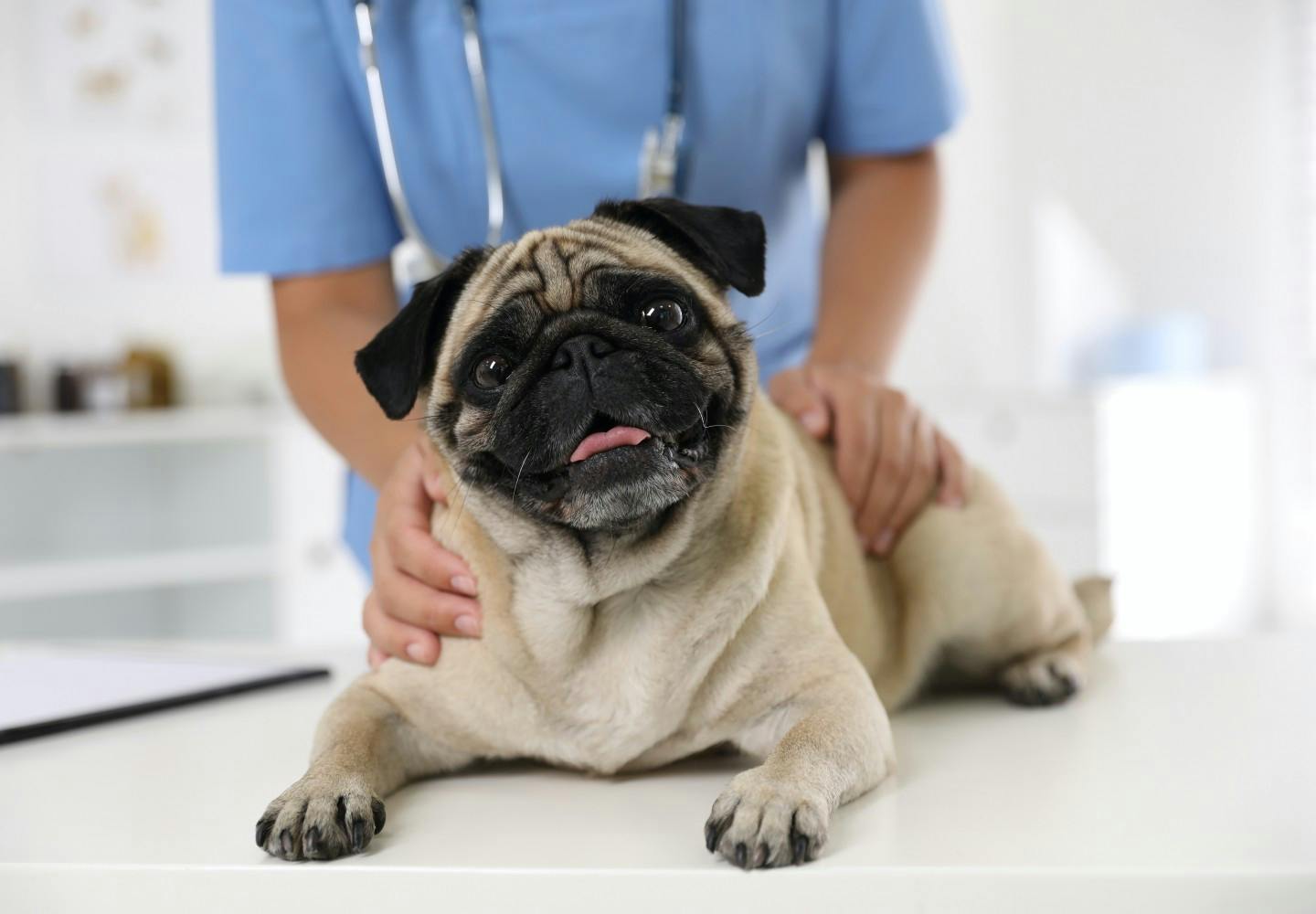
歯石除去や抜歯は、一般の動物病院でも治療ができます。ただし、歯周病がかなり進行してしまった場合などは、歯科専門病院の受診を進められることがあります。では、歯周病の治療内容について見ていきましょう。
歯垢や歯石の除去
麻酔をかけて歯周病の原因となる歯石や歯垢を、専用の機械で除去します。処置費用は2万円前後が一般的です。全身麻酔を行うにあたって事前に血液検査などが必要になります。
抜歯
歯周炎や歯槽膿漏まで症状が発展し、歯の温存が難しい場合は抜歯を行います。切歯や犬歯の歯根が1本なのに対し、前臼歯と後臼歯は歯根が2~3本のため、症状によっては歯をカットして抜く必要があります。また、必要に応じて歯肉の縫合も行うため、すべての治療を合わせると、歯垢や歯石の除去と比べて金額はかなり大きくなるでしょう。
犬の歯周病を予防する方法は?
愛犬が歯周病になると、さまざまなリスクが心配ですよね。歯周病になる前に予防するための方法をご紹介します。
こまめな歯磨き
犬の場合、歯垢が歯石に変わるのにおおよそ2日かかるといわれています。そのため少なくとも2日に1回程度の頻度で歯磨きを行うことが望ましいです。まずは習慣化させることが大事なので、食事や散歩の後など生活習慣の一部に歯磨きを取り入れましょう。
動物病院での歯磨き
動物病院やトリミングサロンで歯磨きをする方法もあります。しかし、月に1回や2週間に1回程度では足りないので、可能なら2日に1回は行きましょう。そうでない場合は自宅での歯磨き習慣をつけることが重要になります。
犬の歯磨きはいつから始めたらいいの?

歯磨きは子犬のうちから始めましょう。まず、大事なのは犬自身が口元を触られるのに慣れてもらうことです。ご自宅に迎え入れたら、さっそく口周りに触れる練習から始め、歯磨きを怖がらない習慣をつけてあげてください。もちろん、飼い主さんが歯磨きの仕方に慣れる努力も必要ですよ。
犬におすすめの歯ブラシは?
犬用の歯ブラシには、タオル・指サック・ブラシなどさまざまなタイプがあります。ただし、犬自身がどの程度歯磨きに慣れているかによって適切なタイプは変わってきます。もし、犬が慣れてきて、やらせてくれるのであれば歯ブラシタイプがおすすめです。無理やり行うと犬も怖がってしまうので、少しずつ慣れさせていきましょう。
犬の歯磨きの頻度と上手に磨くポイントは?

歯を磨く頻度はできれば毎日、難しければ2日に1回のペースで行いましょう。
歯磨きを使うときは自身が使う場合と同様に、鉛筆のように持って力を入れすぎないようにします。慣れるまではご褒美を与えながら行っても良いでしょう。まずは歯磨きに慣れてもらうことが大切です。
奥歯の外側を磨くときは口元を軽く押さえ、上唇をめくりながら歯ブラシを当て磨いていきましょう。裏側を磨くときは、片方の手で上顎を優しく持ち上げ、歯ブラシを持っている手で下あごを押さえながら磨きます。
まず少しの時間から始めてみて嫌がる前にやめる、というのを繰り返していくのがポイントです。
犬に人間の歯磨き粉は使用していいの?
人間用の歯磨き粉は発泡剤が入っているので使用しないでください。必ず犬専用の歯磨き粉を使いましょう。犬の好む味がついていて、刺激が少ないため、歯磨きがしやすい状態を作ってくれるはずです。
犬が歯磨きを嫌がるときの対処法は?

無理やり歯磨きを続行するのではなく、まずは口元を触る練習から行ってください。口元を撫でて、大人しくしていたらご褒美をあげるという行為を繰り返します。慣れてきたらそのまま口の周りを数秒優しく掴んでみましょう。徐々に触れる範囲や時間を増やし、歯にタッチできるまで練習していきます。
犬の歯磨きの代わりになるものは?
犬用の歯磨きガムや歯磨きトイが代わりに使えます。この2つは奥歯を磨く目的であれば代用できます。そのほか歯磨きシートもタオルで歯を拭く代わりとして活用できます。ただし、綿棒は誤食の可能性があるため、使用しないようにしましょう。
※記事内に掲載されている写真と本文は関係ありません。












