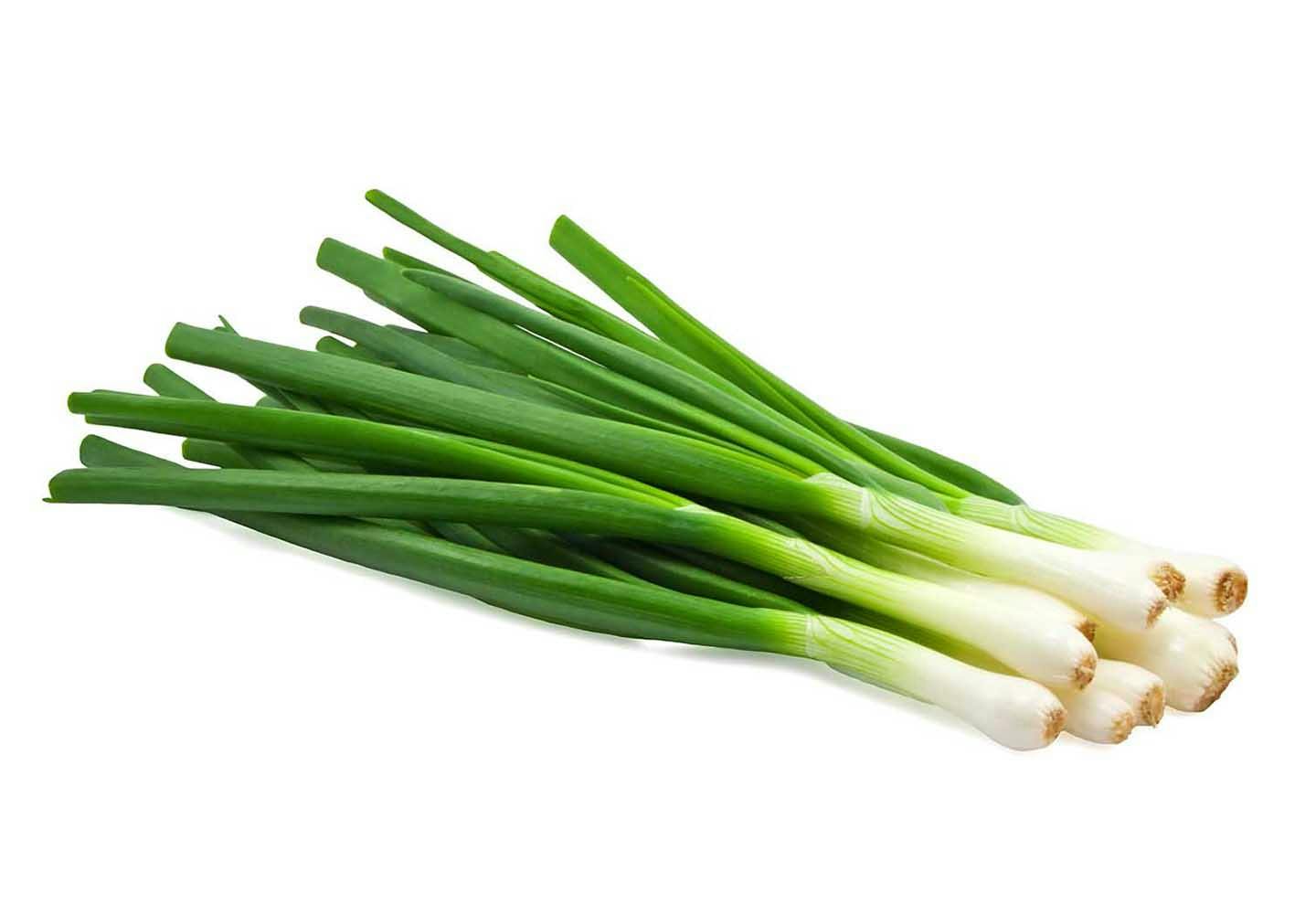2024年02月10日 更新 (2020年08月03日 公開)
chicoどうぶつ診療所所長。体に優しい治療法や家庭でできるケアを広めるため、往診・カウンセリング専門の動物病院を開設。

実は犬にチョコレート製品は厳禁! 場合によっては命に関わる可能性もあるんです。今回は、犬がチョコレートを食べてはいけない理由と、うっかり食べてしまった時の対処法をchicoどうぶつ診療所の所長である林美彩先生に伺いました。
目次
- 犬にチョコレートを与えてはいけない理由は? ココアやお菓子も要注意
- 犬がチョコレートを食べた場合の症状とは?
- 犬がチョコレートを食べてしまった場合の対処法は?
- 犬がチョコレートを食べた時の動物病院での治療について
- 犬がチョコレートを誤食しないための予防策は?
- 犬にはキシリトール入りのガムも危険!
犬にチョコレートを与えてはいけない理由は? ココアやお菓子も要注意
人間にとってはおいしいおやつであるチョコレートですが、実は犬にとっては有害な食品です。原因は、チョコレートに含まれるテオブロミンという成分。人間はテオブロミンを肝臓で無害な物質に代謝できますが、犬は分解能力が弱く、長く体内に留まってしまいます。そのため、毒素を体外に排出しようと下痢や嘔吐などの反応を起こしてしまうのです。多量に食べると神経や心臓へ過剰な作用を起こし、震えや不整脈、けいれんなどの症状が出るほか、最悪の場合は死に至ることもあります。
症状が出始めるのは、摂取後数時間〜半日程度ですが、テオブロミンの毒性自体は72時間ほど続くともいわれているため、摂取後数日間はしっかりと犬の様子を見て、しかるべき対処をとることが重要です。 チョコレートというと板チョコなどを思い浮かべがちですが、テオブロミンはカカオに含まれているのでチョコレート系の製品は全て警戒の対象になります。ココアや、チョコチップの入ったパン、チョコレートアイスなども食べさせないようにしましょう。
テオブロミンが含まれているチョコレート食品の例
・ココア
・チョコパン
・チョコレートアイス
・エクレア
・チョコレートケーキ
・シリアル(チョコレート入り)
・チョコチップクッキー
など
犬がチョコレートを食べた場合の症状とは?

実際に犬がチョコレートを食べてしまった場合、症状は犬の体重と食べたチョコレートの種類・量によって異なります。テオブロミンはカカオに含まれているため、カカオ成分の高いブラックチョコレートの場合、体重5㎏の犬では板チョコ1/6枚程度食べただけでも軽症の中毒症状が現れます。 逆に、カカオ成分の少ないホワイトチョコレートの場合、多量でなければ中毒症状自体が起きないこともありますが、量に関係なく食べてしまった場合には注意しておきましょう。
チョコレート中毒の症状
●軽症の場合
・嘔吐や下痢
・失禁
・水をよく飲む
など 具体的な症状がなくても、落ち着きがなくなる・いつもと様子が違うというケースもあります。
●中程度の場合
・動悸が激しい
・神経過敏
・尿の量が多い
・興奮
・頻脈
など
テオブロミンには犬の心臓の鼓動を激しくする働きがあります。そのため、動悸が激しくなるなど心悸亢進(しんきこうしん)作用が見られた場合には、チョコレート中毒の可能性があるため病院を受診しましょう。
●重症の場合
・けいれん
・震え
・発熱
・不整脈
・昏睡
など
ふらつく、ぐったりしているなどの症状がある場合は危険です。すぐに動物病院に連れて行きましょう。
犬がチョコレートを食べてしまったときの致死量は?
テオブロミンの致死量はおおよそ100〜200mg/kgと言われています。チョコレートの製品・種類によってテオブロミンの含有量が異なりますが、ミルクチョコレート100g中のテオブロミン含有量を250mg程度とした場合、体重5kgの犬では、50gのミルクチョコレート4枚で、致死量となります。
ダークチョコレートやブラックチョコレートなど、カカオ含有量が多いチョコレートの場合、1枚に含まれるテオブロミン量はメーカーにもよりますが、大体500~700㎎程度なので、体重5㎏の犬では、板チョコ1枚程度でも致死量となります。
犬が間違って食べてしまった時には「どんな種類のチョコレートを、どのぐらいの量を食べたのか」を把握することが大切です。獣医師に見せる際、チョコレートのパッケージなどを保管しておき持参するようにしましょう。
犬がチョコレートを食べてしまった場合の対処法は?

愛犬がチョコレートを食べてしまった場合の正しい対処法を以下にまとめました。
犬がチョコレートを食べてしまった場合の対処法
- 動物病院に連絡を入れる
- どんな種類のチョコレートをどのぐらいの量を食べたのか把握する
- 犬の様子や症状を観察する
ここで気を付けたいのは食べたチョコを無理やり吐かせるなど、自宅で対処しようとしないことです。飼い主が吐かせようとして時間をとってしまうと、その分毒素が身体に回ってしまい、犬への負担になります。必ず病院に連れて行きましょう。症状が出るのは、チョコレートを食べてから1〜6時間後が多いと言われています。食べた後すぐに症状が出るとは限らないので、数時間前の様子もあわせて思い出してみましょう。
応急処置は獣医師の指示に従おう
愛犬が苦しんでいる様子を見ると、つい何かをしたくなることでしょう。しかし、素人が判断するとかえって愛犬のためにならないこともあります。犬の体重やチョコレートの摂取量、症状によって対応が異なるため、応急処置に関しては獣医師の判断を仰ぎましょう。
犬がチョコレートを食べた時の動物病院での治療について
食べてから時間が経っていない場合には、病院で催吐処置をしてチョコレートを体内に取り込む前に吐き出させます。テオブロミンを解毒させる薬はないので、時間が経っている場合には、胃洗浄や点滴など様態に応じた処置をおこないます。
犬がチョコレートを誤食しないための予防策は?

愛犬から見ると、チョコレートは大好きな飼い主がおいしそうに食べているもの。「ちょっと自分も食べてみたい」という好奇心を起こしても不思議ではありません。間違って食べることがないように、対策をしてあげたいところですね。
留守の際にはケージに入れる
チョコレートの匂いを覚えている愛犬が、飼い主が留守にしたタイミングにチョコレートを求めて荷物を漁ることもあります。自分の目が行き届かない時は、誤食を防ぐためにも犬をケージに入れておくか、チョコレートを密閉容器に入れておいたほうがいいでしょう。
犬のそばに人の食べ物を置かない
リモートワーク中などで膝に愛犬を乗せている場合、いくら気を付けていても、ふとしたタイミングで食べられてしまうこともあります。大前提として犬のそばに人の食べ物を置かないようにし、不幸な事故が起こる可能性を低くすることが大切です。
食べないようにしつける
「チョコレートは危険なもの」と犬に教えるのも有効な手段です。この場合、チョコレート単体を危険なものと認識させるのは難しいので、「人が許可したもの以外は食べない」としつけるように心がけましょう。
犬にはキシリトール入りのガムも危険!
意外と知られていませんが、実はチョコレートと同じくらい誤飲が多いのがガムやタブレット。しかも、「チョコレートじゃないからいいのでは?」とその危険性を認識していない飼い主さんも少なくありません。全てのガムやタブレットに問題があるわけではなく、キシリトール成分が配合されているものに注意してください。チョコレートに含まれているテオブロミンと同じく、キシリトールも犬にとって危険な成分です。
人も犬も食べ物を食べると消化吸収し、ブドウ糖として体内に取り入れますが、血液中のブドウ糖の濃度(=血糖)が高くなりすぎないように、体内でインスリンを発生させ、調整するようにできています。人がキシリトールを摂取した場合は、そのインスリンの発生をセーブします。そのため、糖尿病などの療養食で用いられることがあります。しかし、犬がキシリトールを摂取すると、逆にインスリンの発生を促してしまうのです。そのため、意識の低下、けいれん、脱力、肝障害、昏睡などを引き起こす恐れがあります。
昨今ではキシリトール成分を配合したガムやタブレットなどの食べ物も数多く販売されています。ついつい机の上に置きっぱなしにしてしまうことが多いので、こちらもチョコレートと同じく気を付けたいところですね。
第5稿:2021年9月16日更新
第4稿:2021年4月15日更新
第3稿:2021年1月27日更新
第2稿:2020年10月19日更新
初稿:2020年8月3日公開
※記事内に掲載されている写真と本文は関係ありません。