2023年03月14日 更新 (2021年04月28日 公開)
博士(獣医学)。専門は獣医動物行動学。大学で教育研究活動の傍ら、動物病院でもしつけや問題行動のカウンセリングを行う
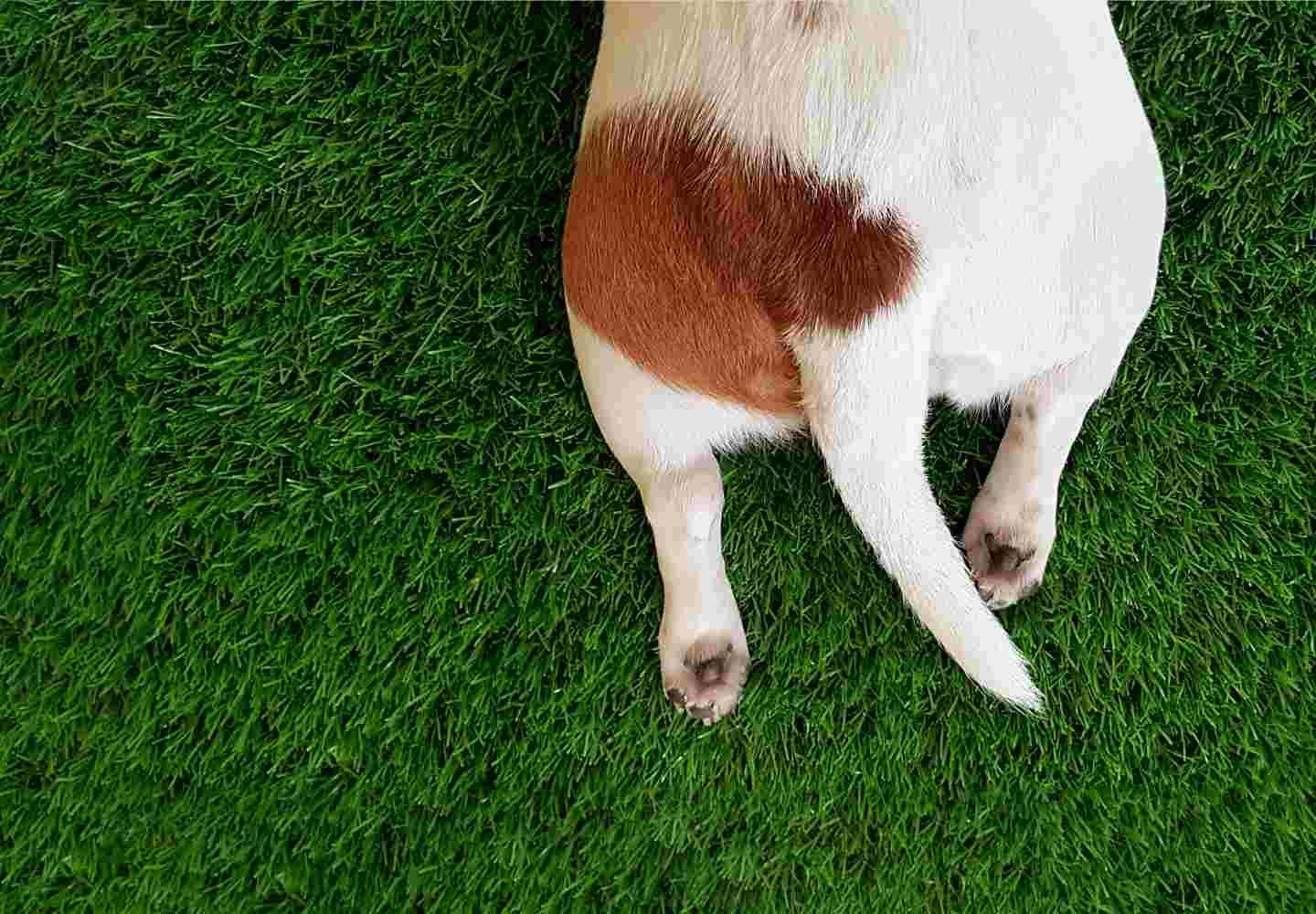
犬が自分の体を舐めるのはごく自然な行動ですが、特定の部分だけをずっと舐め続けていると病気のサインかもしれません。今回は、犬がおしりを舐める主な理由や考えられる病気について、動物行動学を研究する獣医師の茂木千恵先生に伺ったポイントをふまえて解説します。
目次
- 犬がおしりを舐める主な理由は?
- 犬が尻尾のすぐ上や臀部を舐める理由は?
- 子犬やシニア犬がおしりを舐める理由は?
- 犬がおしりを舐めているときに考えられる病気は?
- 犬が頻繁におしりを舐めている場合、飼い主がチェックするべきポイントは?
- 犬が頻繁におしりを舐めているときに気をつけたい異変のサインは?
- おしり関連の疾患になりやすい犬種は?
- 犬が頻繁におしりを舐める場合、自宅でできる対処法は?
犬がおしりを舐める主な理由は?

犬がおしりを舐めるのには、いろいろな理由があります。どんな理由があるのか見ていきましょう。
習性によるセルフグルーミング
犬がおしりを舐めるのは、自分の体を衛生的に保つために大切な作業の一つです。日常生活でたまに見る程度ならいいのですが、頻繁に舐めたり噛んだりするようになったら注意して観察してください。
おしりが乾燥している
おしりが乾燥していると、うるおいを与えようとして舐めることがあります。
汚れや肌トラブル
肛門の周りには清潔にしていても便がわずかながらついているため、傷があると感染症にかかりやすくなります。アトピー性皮膚炎など皮膚の炎症が肛門周囲に起こると、乾燥や湿疹による痒みがおこります。痒みが気になって舐め続けると、さらに皮膚の状態が悪くなっていきます。
うんちのキレが悪い
便が固いときや便の量が少ないと便のキレが悪くなり、便が肛門に残っているような違和感からしきりに舐めようとします。高齢犬は肛門括約筋の筋力が衰えることが多く、キレの悪さも目立ってきます。
虫刺されや寄生虫
肛門周囲は被毛が薄く外からの刺激に弱い部分です。虫に刺されたり外部寄生虫に寄生されたりして痒くなったり痛みを感じることがあり、それが刺激となって舐めようとすることもあります。
また、犬の腸内に生息するサナダムシ、回虫、鞭虫といった内部寄生虫は、肛門に炎症が起こる原因となったり、下痢などの便の性状を悪化させたりします。これらの寄生虫の断片は、犬の肛門の周りや便にも見られることもあります。そのため、肛門が気になって舐めてしまうのです。
病気
肛門腺(肛門のう)や肛門周囲腺の炎症なども犬がおしりを舐める理由の一つです。健康な肛門腺は通常、犬が排便するたびに臭い液体を排出します。何らかの原因で肛門腺に細菌感染が起こると強い痒みと痛みが起こります。すると、犬は患部を舐めるだけでなく、おしりを床にこすりつけるなどして傷を作ってしまい、さらに腫れたり感染が広がって慢性化することもあります。
その他
犬がおしりを舐める理由に、直脱腸も考えられます。直腸脱は、直腸の1つまたは複数の層が肛門から突き出ている状態です。重度の下痢、または頻回に排便する犬に発生します。
犬が尻尾のすぐ上や臀部を舐める理由は?
犬がおしりから少しずれた場所を舐めているときは理由が変わります。まず、考えられるのがノミ、そして心因性の行動です。尻尾や尻尾の付け根、臀部を舐めているときは神経障害、あるいは強迫性の問題行動を示している可能性があります。
そのほかの理由としては、学習した行動である可能性もあります。おしりとは微妙に違う部分を舐めていたら飼い主さんがかまってくれたなど、犬にとって嬉しいことが起こると「舐めたら良いことが起こる」と記憶しその行動を繰り返しているのです。
子犬やシニア犬がおしりを舐める理由は?
子犬やシニア犬の場合は、肛門括約筋のコントロールが未熟であったり、筋力が弱くなったりしています。便を一度に出し切ることが難しいため、残量感が気になって肛門を舐めることが考えられます。
子犬の場合は、もう一度トイレにつれて行ったり散歩で軽く走らせてあげたりすると便が出やすくなります。シニア犬の場合は、便の性状が柔らかくなるように、水溶性の食物繊維と水分を意識した食事に変えてみましょう。
犬がおしりを舐めているときに考えられる病気は?
 犬がおしりを舐めている時に考えられる主な病気には、肛門のう炎、肛門周囲腺腫、会陰ヘルニア、皮膚炎があります。それぞれどういった病気か解説します。
犬がおしりを舐めている時に考えられる主な病気には、肛門のう炎、肛門周囲腺腫、会陰ヘルニア、皮膚炎があります。それぞれどういった病気か解説します。
肛門のう炎
犬の肛門のうは、マーキングに使う分泌液を出す部分です。この肛門のうが炎症を起こすと強い痛みをともないます。一番わかりやすい症状はおしりを床につけたまま前に進む行動です。こういった行動が見られたら、獣医師に相談しましょう。
肛門周囲腺腫
肛門やおしりの周りの皮膚にある皮脂腺が腫瘍になってしまう病気です。未去勢のオスや避妊済みのメスに見られます。肛門のまわりで気になるできものがあったら動物病院に連れて行きましょう。
会陰ヘルニア
ヘルニアは中に収まっているはずの臓器などが脱出してくる病気です。会陰ヘルニアは、肛門から直腸や膀胱などの臓器がはみ出してしまうことを指します。臓器によっては命に関わることもあるため、愛犬の肛門に異常が見られたらかかりつけの獣医師の診察を受けましょう。
皮膚炎
おしり付近に傷があると、そこから細菌に感染して皮膚炎を起こすことがあります。アトピー性皮膚炎は、柴犬、フレンチ・ブルドッグ、シー・ズー、ウエスト・ハイランド・ホワイト・テリアに起きやすいので注意が必要です。
犬が頻繁におしりを舐めている場合、飼い主がチェックするべきポイントは?
犬がおしりを舐めるのは珍しいことではありませんが、ずっと舐め続けていることは正常ではありません。 しかし、同時に体の他の部分も噛みながらおしりを舐める、おしりを床に擦り付ける、嘔吐や下痢を繰り返す、肛門の周りに炎症または体の他の部位の皮膚に炎症があるといった症状のいずれかに気づいたら、動物病院で獣医師の診察を受けましょう。
犬が頻繁におしりを舐めているときに気をつけたい異変のサインは?
 犬が頻繁におしりを舐めているとき、下記のような症状が出ていたら病気や不調のサインかもしれません。
犬が頻繁におしりを舐めているとき、下記のような症状が出ていたら病気や不調のサインかもしれません。
おしりをしきりにかく
寝ているときにも不意に起きて、おしりをかいたり舐め続けたりする場合は痒みを感じています。動物病院で診察してもらいましょう。
おしり歩きをする
肛門のうの中に分泌物が蓄積していると、気になっておしりを床にこすりつけるように前進することがあります。放置すると肛門周囲に傷ができて感染が起こったり、その他の重大な疾患に発展したりすることがあるので注意が必要です。
しこり、できものが確認できる
肛門周囲腺腫や会陰ヘルニアである可能性があります。
排便時に痛がる
なんらかの傷ができているか、見えない部分にしこりやできものができている可能性があります。
おしりの近くを触ると怒る
肛門のう炎の場合は強い痛みがあるため、飼い主さんがおしりの近くを触ろうとしただけで怒ります。
汁が出ている
肛門内に膿が溜まっていたり、皮膚炎になっていたりする可能性があります。
排泄時に出し渋る、出ない
普段の食事の内容を変えた、おやつにいつもと違うものを与えたといった場合は、数日間は排便に異変がないか観察し、排便困難が続くようなら動物病院へ。この他、慣れない場所に出かけたなどの心当たりがあれば、1日ほど様子を見て便の調子が戻れば大丈夫です。
おしり関連の疾患になりやすい犬種は?
肛門のう炎は、ミニチュア・プードル、トイ・プードル、チワワなどの小型犬種がなりやすく、大型犬には起こりません。また、他の犬種より肛門周囲腺が多いジャーマン・シェパード・ドッグは、肛門の周りに腫瘍ができて肛門周囲瘻(ろう)にかかりやすいと言われています。
犬が頻繁におしりを舐める場合、自宅でできる対処法は?
 病気が原因である場合、ドッグフードに水分を取り入れるなどして便の固さを調整してあげましょう。水溶性食物繊維は大腸の中でも水分を保持できて便が柔らかくなるためオススメです。
病気が原因である場合、ドッグフードに水分を取り入れるなどして便の固さを調整してあげましょう。水溶性食物繊維は大腸の中でも水分を保持できて便が柔らかくなるためオススメです。
心因性である場合には、日頃からストレスを与えないよう気をつけましょう。ストレスの原因を取り除いたり、リフレッシュできるような遊びを取り入れて生活環境を整えるのもいいですね。
また、飼い主さんの中には排便後に犬のおしりを拭く方もいますが、市販のウェットティッシュはアルコールなど犬にとっての刺激物が含まれている可能性があるため、避けた方が無難です。
※記事内に掲載されている写真と本文は関係ありません。













