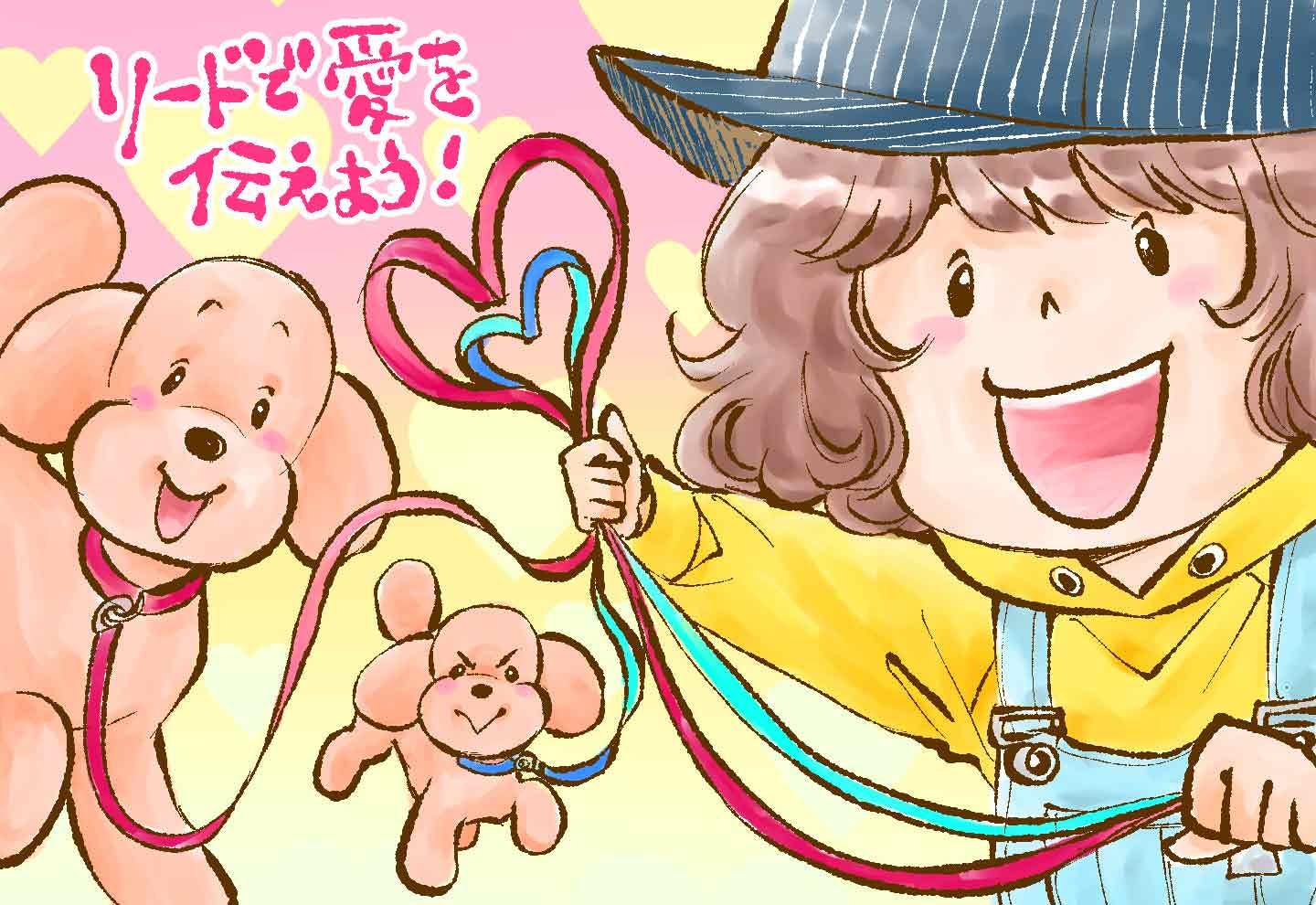2023年12月06日 更新 (2022年07月10日 公開)
chicoどうぶつ診療所所長。体に優しい治療法や家庭でできるケアを広めるため、往診・カウンセリング専門の動物病院を開設。

首輪に比べて犬の体にかかる負担が少ないといわれている犬のハーネス。しかし、実際のところどのようなメリット・デメリットがあるのかがわからず、使用を迷っている飼い主も多いのではないでしょうか? 今回の記事では、ハーネスを使用するメリット・デメリット、負担の少ないハーネスの選び方や付け方のコツなどをchicoどうぶつ診療所所長で獣医師の林美彩先生に解説していただきます。
目次
- 犬にハーネスを使用するメリットは?
- 犬にハーネスを使用するデメリットは?
- ハーネスを使用するのが向いている犬は?
- 犬用のハーネスの種類は?
- 犬の負担が少ないハーネスの選び方は?
- 犬への負担が少なくなるようなハーネスの正しい付け方は?
- 犬がハーネスを嫌がる場合の対処法は?
- 犬の脱走に備えてハーネスにも迷子札をつけよう
犬にハーネスを使用するメリットは?
まずは、首輪に比べて、ハーネスを使用するメリットはどこにあるのかを詳しく見ていきましょう。
脱走の危険性が低くなる
首輪の場合は、何かの拍子に頭部がすり抜けて脱走してしまうことが考えられます。一方、ハーネスの場合は、前足から上半身を包み込む形になっているため、首輪より抜けにくく、脱走のリスクが低くなるでしょう。
犬の体にかかる負担が少ない
首輪の場合には、頚部(けいぶ:頭部と胴部をつなぐ部分、首)への負担がかかり、呼吸器への負担なども懸念されます。ハーネスの場合には胸部や胴部が装着面になることから、頚部や呼吸器にかかる負担が首輪よりも軽くなるといわれています。
いざという時に愛犬を制御しやすい
ハーネスは犬の装着範囲が広い分、いざという時にも飼い主が犬をつかみやすい、制御しやすいと考えられます。
落ち着いて散歩ができる犬になる
ハーネスは装着範囲が広く、犬の制御が効きやすいため、しっかりトレーニングを行えば、落ち着いた散歩ができる状態になります。
犬にハーネスを使用するデメリットは?
ハーネスを使用するメリットもありますが、一方で以下のようなデメリットも考えられます。
犬の引っ張り癖が増すこともある
首輪だと引っ張った際に犬の頚部に負担がかかるので、「引っ張られると苦しい」という認識から引っ張り癖が落ち着くことがあります。しかし、ハーネスの場合には頚部や呼吸器への負担がかかりにくいことから、引っ張っても苦しくないため、引っ張り癖が定着したり、増してしまったりする可能性が考えられます。
足の短い犬種はハーネスが体から抜けやすい
ハーネスは前足に通して装着するので、足の短い犬種では、前足が抜けやすく、ハーネスが外れやすい場合もあります。
ハーネスを使用するのが向いている犬は?
以下のような特徴を持つ犬は、ハーネスの使用が向いているといえます。ハーネスが向いている理由をそれぞれ見ていきましょう。
老犬(シニア犬)
ハーネスを使用すると頚部や呼吸器への負担が軽くなる、犬の体にかかる負担が分散されることから、体が弱ってきているシニア犬に向いているでしょう。
呼吸器官が弱い犬
首輪の場合には頚部、呼吸器への負担が考えられますが、ハーネスであれば前肢を通して上半身全体を包み込む形になるため、呼吸器への負担軽減が期待できます。
散歩に慣れていない子犬
子犬は体が小さいために首輪が抜けてしまいやすい上、散歩に慣れていないので、何かの拍子に脱走する可能性が高いです。上半身を覆うことができるハーネスは、しっかりと装着できるので、子犬の脱走リスクの軽減につながります。
犬用のハーネスの種類は?
ハーネスの種類によって形状や装着方法、特徴もさまざまです。ハーネスによる負担を少なくするためには、これらの種類の中から愛犬に合ったものを選ぶことも大切です。

H型
従来からあるポピュラーな形で、前足を通すための大きな2つの輪にベルトが2本付いています。ただし、ハーネスに前足を通して使用する必要があるので、前足に触れられるのを嫌がる犬の場合には装着が難しいケースも。8の字型のハーネスと比較すると、ベルトにかかる力が分散されるため、犬の体への負担は軽いでしょう。

8の字型
頚部と胴体に輪を通して使用するタイプで、その2つの輪が「8の字」に見える形のハーネスです。前足に触れることなく装着が可能のため、H型の装着が難しい子でも使用できる形になっています。

ベスト型
生地の面積が広く、比較的柔らかい素材で作られているものが多いため、引っ張った時に犬にかかる力が分散されやすい特徴があります。体への負担をなるべく軽くしたい犬に適しているでしょう。

イージーウォークハーネス(ひっぱり防止用ハーネス)
リードをつなぐ部分が、犬の胸元にあるタイプです。ひっぱられた方向と逆方向に力をいれ進もうとするという犬の習性を利用して、引っ張り癖や飛びつき癖を抑えることを目的としたハーネスです。
犬が前にリードを引っ張ると前胸部に負荷がかかるので、自然と後ろ方向に力が入って前に進みにくくなります。頚部や呼吸器の負担を軽くしたいけど引っ張り癖がある子におすすめです。
犬の負担が少ないハーネスの選び方は?
毎日のように使うものなので、せっかくならなるべく愛犬への負担が少ないハーネスを選んであげたいですよね。ハーネス選びの際には、以下のようなことに気をつけましょう。
試着させて、愛犬に合う種類・サイズを選ぶ
前述したようにハーネスにはさまざまな種類があります。可能な限り試着させて、どの種類が愛犬にとってストレスなく装着でき、負担がないかを確認しましょう。次に、きちんと愛犬の体のサイズをはかって、体に合ったサイズのハーネスを選びます。サイズが合っていないと負担がかかってしまったり、ハーネスが抜けてしまい脱走リスクも懸念されます。
愛犬の体のサイズの変化に合わせて買い直す
子犬から成犬へと成長していく過程でサイズも変わります。お金はかかりますが、体の成長に合わせてその都度サイズを計測し、ハーネスを買いなおすことも必要になるでしょう。また、犬がダイエットをしてやせた時、逆に太ってしまった時にもハーネスのサイズが変わる可能性があります。
犬が洋服を着るか・着ないかによってサイズを選ぶ
犬が洋服を着てハーネスを装着するのか・着ないで装着するかによってもハーネスのサイズは変わります。装着するたびにきちんと愛犬にフィットしているかどうかを確認することも重要です。
足が短い犬種のハーネスの選び方は?
H型や8の字型は基本的に抜けにくい構造といわれていますが、どのハーネスの種類でも抜けてしまうリスクはありますし、構造が煩雑なものは装着時の手間がかかってしまいます。足が短い犬種の場合も、愛犬に合った種類とサイズを試着した上で選ぶのが確実でしょう。
犬への負担が少なくなるようなハーネスの正しい付け方は?

犬の体とハーネスの間に隙間がなくても苦しくなりますし、隙間がありすぎると脱走リスクが考えられます。指1本分程度が入る余裕があるようにサイズを調整し装着させましょう。
犬がハーネスを嫌がる場合の対処法は?
ハーネスを嫌がる犬には、焦らず少しずつ慣らしていくことがポイントです。H型であれば、片足を通したらおやつを与える、8の字型であれば首を通せたらおやつを与えるなど、ステップを踏んで少しずつクリアしていきましょう。
子犬の頃から装着してなれさせる
上半身を包み込む形になっているので、成犬になってから装着する場合には圧迫感のようなものから嫌がってしまう子も少なくありません。子犬の時から装着させて慣れておくことで、ハーネス装着によるストレスを軽減できると考えられます。