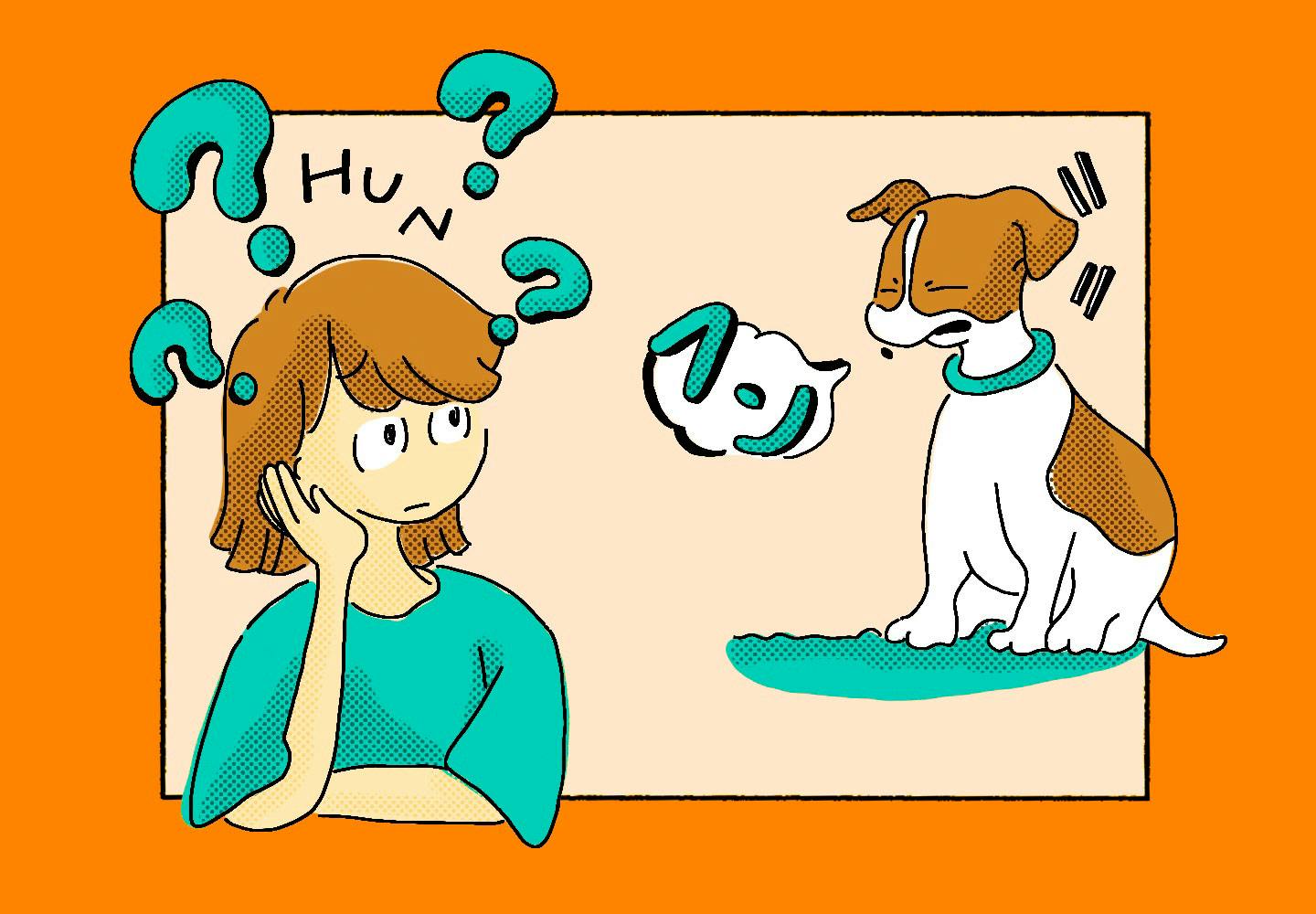2023年10月18日 更新 (2020年02月28日 公開)
アメリカ獣医行動学会会員、ペットの行動コンサルテーション Heart Healing for Pets 代表。問題行動の治療を専門とし臨床に携わる。

垂れた耳と3色の短い毛色が特徴のビーグル。小型犬ながらとてもエネルギッシュで遊ぶことが大好きな犬種です。食欲旺盛な子も多いので、肥満に気をつけた食事を与えるなど、ビーグルならではの飼い方のポイントを知っておくことも大切です。そこで今回は、「ペットの行動コンサルテーション Heart Healing for Pets」代表で獣医師の石井香絵先生に教えていただいた、ビーグルの性格の特徴や、しつけの仕方、飼育する上での注意点などを解説していきます。
目次
- ビーグルの歴史やルーツは?
- ビーグルの体高・体重は?
- ビーグルの平均寿命は?
- ビーグルの毛色の種類や特徴は?
- ビーグルの性格の特徴は?オスとメスで違いはある?
- ビーグルを飼うのに向いている人は?
- ビーグルの外見や吠え声の特徴は?
- ビーグルがかかりやすい病気は?
- ビーグルの日常のお手入れで気をつけることは?
- ビーグルに食事を与える際の注意点は?
- ビーグルにおすすめの遊びやトレーニングは?
- ビーグルを飼う際の注意点は?
ビーグルの歴史やルーツは?
ビーグルは、イギリスのエリザベス1世(1533~1603年)の時代に、嗅覚を利用して野ウサギを狩る猟犬(セントハウンド)として活躍していたハウンド種が起源といわれています。このハウンド種には大柄な犬種と小柄な犬種がいて、小柄なほうを「ビーグル」(フランス語で「小さい」という意味)と名付けたそうです。当時は、現在のビーグルよりももっと小さく、サドルバックに入れて運ぶことができるほどコンパクトな体つきでした。
ビーグルの体高・体重は?
小型犬に分類されるビーグルの平均的な体高と体重を確認しておきましょう。
体高
平均的な体高は、オスは約36~41 cm、メスは約33~38cmです。
体重
平均的な体重は、オスは約10~11kg、メスは約9~10kgです。
ビーグルの平均寿命は?
ビーグルの平均寿命は12~15歳といわれています。世界で最も長生きをした犬の中に、アメリカで暮らしていたビーグルがいます。「ブッチ」という名前の男の子で、28歳まで生きました(1975~2003)。
ビーグルの毛色の種類や特徴は?
短く、艶のある被毛で体を覆われているビーグル。ここからは、ビーグルの毛色の種類や毛質など被毛の特徴をご紹介します。
【主な毛色】

トライカラー(ハウンドカラー)
大半のビーグルがブラック、ホワイト、ブラウンの3色で構成されているトライカラー(3つの色という意味)の毛色です。ハウンドによく見られるカラーバリエーションのため、「ハウンドカラー」とも呼ばれます。ベースの色はホワイトで、そこにブラウン、ブラックの模様が表れます。

レッド&ホワイト
赤みがかった茶色とホワイトの2色で構成される毛色です。赤みかがった茶色にも個体によって明るめ、濃いめなどバリエーションがあります。

レモン&ホワイト(レモンカラー)
「レモン」と呼ばれていますが、正確には黄色ではなく、赤みがかった茶色をさらに薄めたような色です。この薄い茶色とホワイトの2色の毛色で構成されます。
【被毛の特徴】
ビーグルの被毛は、短毛のダブルコート(上毛と下毛の二層構造)です。短い毛のため毛が絡まることはありませんが、抜け毛がかなり多いので、毛が生え変わる換毛期だけでなく、毎日こまめにブラッシングをしてあげましょう。
ビーグルの性格の特徴は?オスとメスで違いはある?
ビーグルはどのような性格の犬種なのでしょうか? 主な特徴をご紹介します。
明朗快活でエネルギッシュ
ビーグルは明るくて元気な性格の犬が多く、遊ぶのも大好きです。攻撃性を見せることは少ないですが、独特の吠え声でよく吠えます。
寂しがり屋
寂しがり屋な一面があり、分離不安症といって、ひとりにされると不安になり過度に鳴いたり、破壊行動をしたり、不適切な排泄をする不安症になりやすい犬種です。子犬のうちから愛情を十分注ぎ、飼い主との信頼関係を構築すると同時に、ひとりで留守番させたり、ひとりで遊んだりできるよう独立心を養うことを意識して育てることが大切です。
集中力散漫になることも
嗅覚を使って狩猟する猟犬のため、気になるにおいをみつけると集中力が散漫になり、飼い主の声が届かなくなることもあります。
オスとメスで性格に違いはある?
オスのほうがメスと比較すると活発で甘えん坊です。犬種として攻撃性は低いですが、オスのほうが防衛行動がでやすい傾向がみられます。メスはマイペースで天真爛漫な一面を持っている個体が多くいます。
ビーグルを飼うのに向いている人は?

ビーグルには、人によって飼育の向き・不向きはあるのでしょうか?
ビーグルは初心者向きの犬?
初心者向きとはいいにくい犬種です。体はコンパクトですが力が強く、いたずらや破壊行動、拾い食い、吠えの問題など、適切なしつけを適切なタイミングで行わないと悩みがつきません。
ビーグルを飼うのに向いている人は?
エネルギッシュなビーグルの運動要求と愛情要求を十分に満たしてあげることができる人に向いています。散歩やジョギングなどアクティブに動くことが好きな人、しつけやトレーニングに十分な時間を割くことができる人とは相性がよいでしょう。
ビーグルの外見や吠え声の特徴は?
ビーグルの外見や吠え声にはどのような特徴があるのでしょうか?
外見
骨太で筋肉質、大きなたれ耳が特徴的です。群れで狩りをするハウンド系の中で最も小さい体つきをしています。
吠え声
よく通る大きな声で吠えます。一度この吠え声を聞くと、姿は見えなくても声を聞くだけでビーグルが吠えているとわかるほど特徴的な吠え声をしています。
ビーグルがかかりやすい病気は?
愛犬と長く一緒に過ごすため、病気の予防には気を配りたいものです。ビーグルがかかりやすい病気とその予防法や治療法について知っておきましょう。
椎間板ヘルニア
背骨の間にある、クッションのような役割をしているゲル状の物質を「椎間板」と呼びます。椎間板ヘルニアは、椎間板の中心にある髄核が飛び出し、脊髄を圧迫することで脚に麻痺が生じたり、痛みがでたりする神経の病気です。重度になると歩けなくなったり、排尿がコントロールできなくなったりします。発症原因は、激しい運動や肥満、老化、遺伝によるものなどさまざまです。
ビーグルは軟骨異栄養症性犬種であり、椎間板の変性が若いうちから見られることがあります。抱っこをしたら鳴く、腰を痛そうに丸めているなどの症状が診られたら早めに診察を受けましょう。予防するには、フリスビーなどの過度な運動は避けながら、肥満にならないように日々体重を管理することが大切です。
外耳炎
ビーグルは耳が垂れ下がっており、通気性が悪くなることで外耳炎になりやくなります。外耳炎の原因はアレルギー、ダニ、細菌、真菌などさまざまです。外耳炎になると、何度も頭を振ったり、しきりに耳を掻くしぐさをしたりします。また、耳垢が増えたり、赤く炎症することもあります。原因によって治療法も変わりますので、耳の異常に気づいたら早めに動物病院で診てもらいましょう。
チェリーアイ
ビーグルは遺伝的に目の病気にかかりやすい犬種です。チェリーアイ(第三眼瞼突出)と呼ばれる目頭の内側の瞬膜が赤く丸く腫れて、目頭から出てきてしまう病気になることがあります。再発をくり返す場合は、外科的手術により元の位置に埋没させて縫合します。
緑内障
緑内障は眼球内の眼圧が上昇し、激しい痛みや視覚障害が起こる病気です。ビーグルは緑内障を発症しやすい犬種です。眼をしょぼしょぼさせて痛そうにしたり、光に対して過敏に反応しているときは、早めに眼科専門の獣医師に診てもらいましょう。目の病気は早期発見・早期治療が大切ですので、いつもと様子が違うと思ったらすぐに診察を受けましょう。
白内障
白内障は水晶体が白濁する病気です。水晶体が濁ると、まるですりガラス越しに物を見ているようなぼんやりとした視界になります。進行すると物にぶつかったり、つまずいたりして、日常生活に支障をきたす恐れもあります。初期には気づきづらいこともありますが、夜に散歩に行くのを嫌がり、不安や苛立ちが増える犬もいます。予防や進行を遅らせるため、抗酸化作用のあるサプリメントの活用や、強い紫外線を直接見ない工夫(散歩の時間を配慮、犬用サングラスを使うなど)をしてあげましょう。
誤飲、誤食
ビーグルは食欲旺盛で、いたずら好きの犬が多く、拾い食いや異物を誤飲、誤食してしまうことがあります。室内では、いたずらされて困るものや危ないものは犬の口の届かないところで管理しましょう。
また、屋外での拾い食いの習慣がつかないように、散歩中も飼い主とコミュニケーションをとる習慣をつけ、飼い主を意識して歩く練習をすることも大切です。万が一、異物を口にいれてしまったら、「だして」などの号令で、から素直にものを回収できる練習を日頃から行うと、いざというときに役立ちます。
ビーグルの日常のお手入れで気をつけることは?
ビーグルの日常のケアで特に大切なのが耳のお手入れです。大きく垂れた耳は、耳の中の通気性を悪くして外耳炎の原因になることがあります。特に、梅雨時期は皮膚炎や外耳炎が悪化しやすい季節ですので、炎症を悪化させないように、定期的に耳の汚れを拭き取るなどお手入れをしてあげましょう。
ビーグルに食事を与える際の注意点は?
健康な体を維持するためにも、日々の食事選びはとても重要です。ビーグルの食事では、どのような点に気をつけるべきなのでしょうか?
肥満予防のためにフードは適正量を与える
ビーグルは食欲旺盛のため、主食、副食どちらも与えすぎると肥満になります。食べたい要求が大きい場合は、満腹感を得られてカロリーが低い食事に切り返えるとよいでしょう。早食い防止の食器を活用して、食欲を上手に満たしてあげる工夫も有効です。
関節をサポートする成分のフードを与える
ビーグルは関節の病気にかかりやすい犬種です。関節をサポートする成分が含まれたフードを食事に取り入れるのもおすすめです。
スヌードや長い耳専用の食器を使う
ご飯を食べる際に大きな耳が食器の中に入ってしまい、食事の邪魔になったり、耳が汚れたりする心配がある場合は、スヌードを装着したり、長い耳専用の食器に切り替えてあげましょう。
shared-detail.post-related
愛犬を理解するヒントに。 アニマルコミュニケーターのセッションに密着
shared-detail.post-related
犬の健康診断は何歳から受ければいい?検査内容や費用感、必要な理由などについて解説【獣医師監修】
shared-detail.post-related
愛犬に最適なトイレトレーとは?トイレトレーを選ぶポイントを解説
shared-detail.post-related
犬の糖尿病の症状とは?原因や治療法、予防のポイントなどについて解説【獣医師監修】
shared-detail.post-related
犬の目が白いのは白内障?見極めるポイントと病院に連れて行くべき症状について解説【獣医師監修】
ビーグルにおすすめの遊びやトレーニングは?
ビーグルは猟犬のため、エネルギッシュでスタミナにあふれています。いたずらや問題行動を引き起こす多くの犬は、運動や遊びが十分でないことが原因であることも多いため、毎日の散歩や遊びを介して、体をしっかり動かしストレスを軽減させてあげましょう。嗅覚が優れている犬種のため、鼻を使った遊び(スナフルマットや知育玩具を使用)やトレーニングを行うと本能行動が満たされます。
ビーグルを飼う際の注意点は?

最後に、ビーグルを飼うときの注意点を確認しておきましょう。
床で滑らないように工夫する
ビーグルは活発な犬種ですので、屋内では床に滑り止めのマットをしくなど滑らない工夫をしてあげましょう。椎間板ヘルニアや膝蓋骨脱臼などの病気の予防にもつながります。
誤嚥しない環境づくりをする
いたずらをして異物を誤嚥することもあります。特に若くいたずら好きなビーグルと暮らす場合は注意が必要です。口に入れてしまう恐れがある物を愛犬の行動範囲に置かないなど、環境を整えていたずらできないようにしましょう。
※記事内に掲載されている写真と本文は関係ありません。